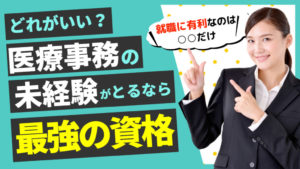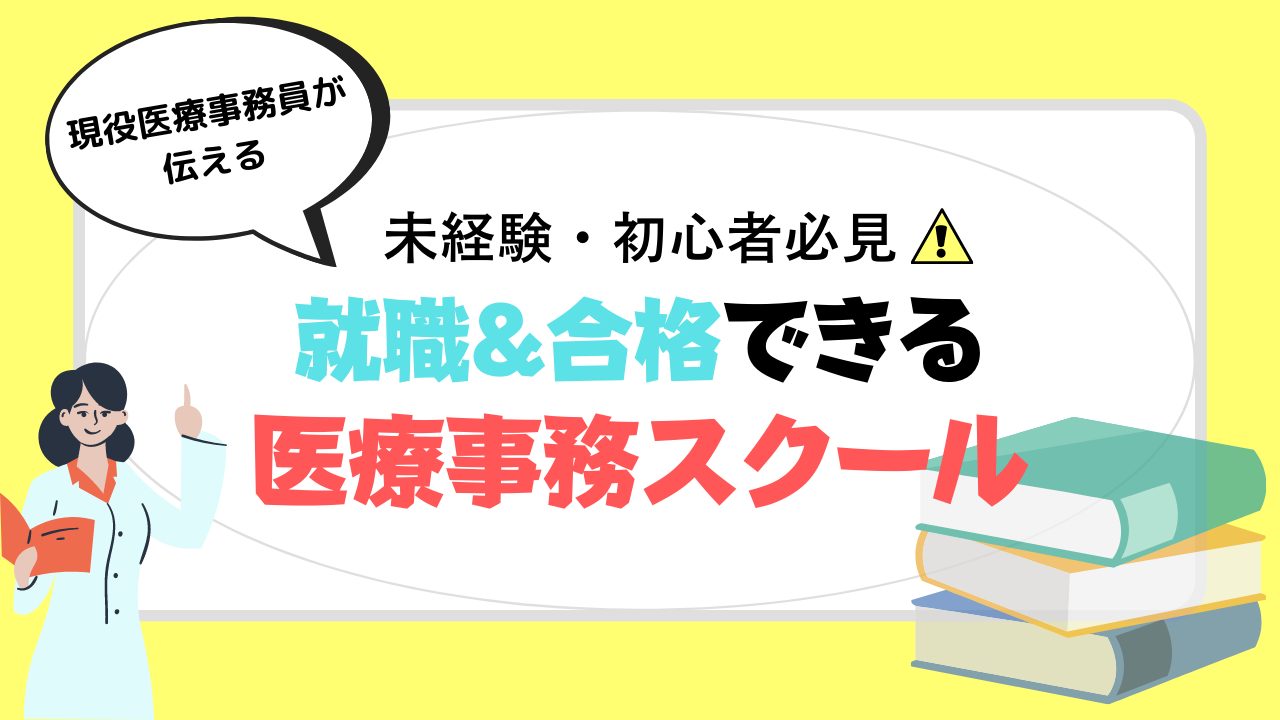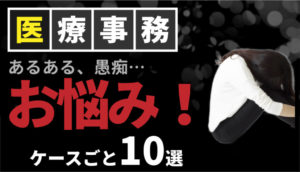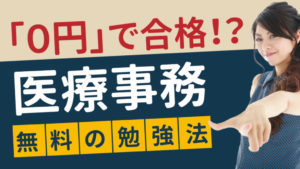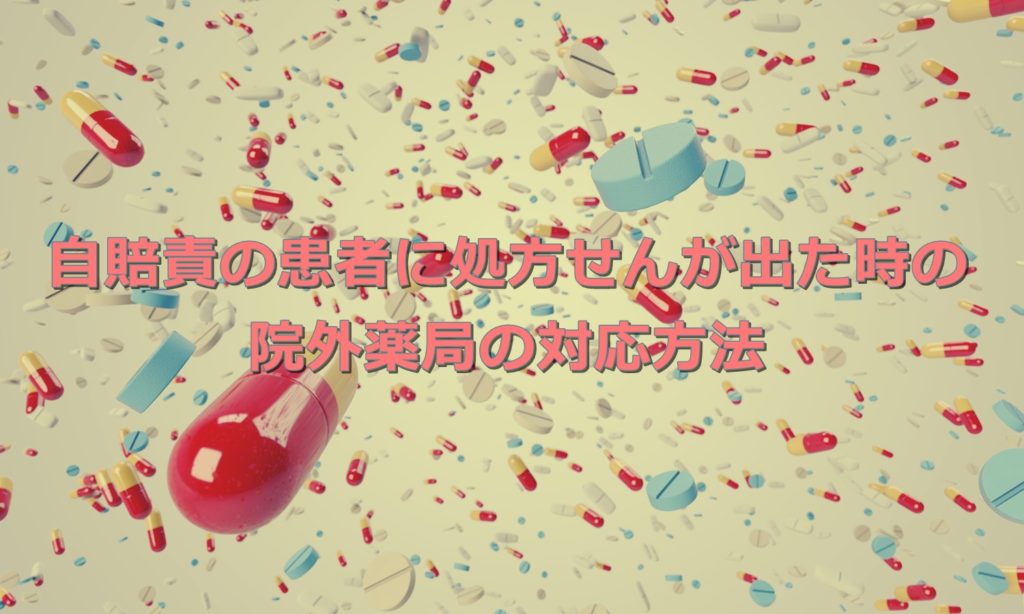自賠責患者が来た時の対応はこちらの記事で詳しく書いてあります。
⇒自賠責・第三者の請求方法までの流れと対応 ~事故の患者がきた場合~
しかし、これはどっちかというと医療機関向けに書いた記事でした。
今回は、事故の患者さんで処方せんがでた場合の、院外薬局目線での対応について書いて行きます。
(私が薬局に勤務したことがないので、医療機関と薬局がやりとりするときの流れをメインに書いて行きます。)
病院とやり取りする
事故患者の情報は、通常であれば本人からの申し出であったり、事前に保険会社さんからの連絡で知ることができる情報だと思います。
しかし、保険会社から連絡がなかった場合というのは、薬局はどうすることもできないはずです。
なぜなら、処方せんの保険内容を決めるのは医療機関である病院だからです。
院外薬局としては、その処方箋の保険に従い、薬を処方するだけといった具合になります。
つまり、病院の情報なしでは薬局もレセプト請求ができなくて困ってしまう。
ということになってしまうんですね。
どうやって自賠責の情報を入手するか
初歩的な対応にはなりますが直接、病院に事故患者の情報を聞くということが大事になってきます。
もちろん、薬局側で情報が判れば、そこで完結できるのでしょうが。
ほどんどの薬局が、門前薬局なので主にやりとりをしている病院があるはずです。そこへの確認が大事です。
また、門前以外だったとしても、処方せんを発行した医療機関へ問い合わせるのが一番確実かもしれませんね。
自賠責患者に処方せんがでたときの具体的な対応
自賠責と確定している場合
保険が、自賠責と確定している場合には処方箋にも自賠責の情報が記載されていると思うので問題はないと思います。
また、保険会社からも連絡が来ていれば、尚よいです。
自賠責と確定していない場合
こっちのケースの方が面倒くさくて、さらに、実務ではこっちのケースの方が多いかもしれません。
事故患者で自賠責と確定していない場合はどうするのかというと、とりあえずは自費での取り扱いになります。
基本的に事故で保険証は使用できないという考えのもとです。
※正確には保険証は使えますが、病院や薬局の初期対応としては、自費でもらってもいいのではないかと個人的には思っています。
臨機応変に保留にする
自費でとりあえずもらっておくのが未収にもならないし、ベストな選択肢だとは思いますが、自費でもらってしまうと後から返金するのが面倒だったり、患者さんにも再度、足を運んでもらわないといけないというデメリットもあります。
そこで、自費でもらわくなくてもいいというのであればとりあえず保留というかたちをとります。
そのほうが患者さんの負担も減るし、返金作業という面倒もなくなります。
ただし、ここは未収にも繋がる微妙なラインだと思うので各病院の判断にはなってくると思います。
とりあえずレセプトに間に合わせる
保険情報が判らないまま、月をまたいでしまう状況も多々あるとおもいます。
その中で一番大事なのは、レセプト請求時(10日)まで、事故患者の情報を入手し、請求できるようにしておく。
ということが優先事項になってきます。
私の病院でも月をまたぐと、いろいろな院外薬局から
『事故患者は自賠責でいいのか?』
『請求先の保険会社を教えてくれ』
といった内容の問い合わせがきます。
まとめ
一番よいのは、病院と同じように薬局でも詳しい情報を聞き出すのが一番かとは思います。
ただ、門前薬局の場合はそこまでしなくても病院から情報を入手できると思うので、そちら優先に考えてもいいのかなと思います。
大事なのは、病院といかに上手く連携がとれるかということだと思います。