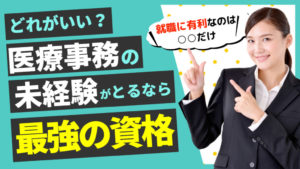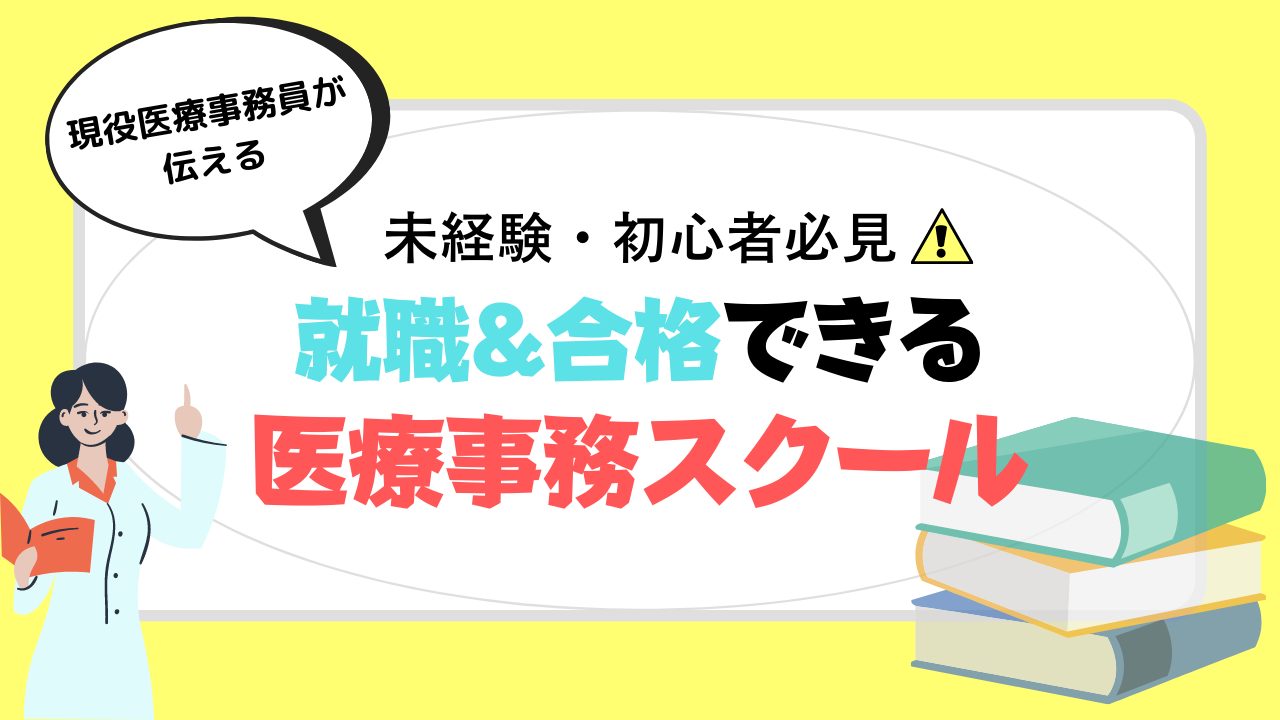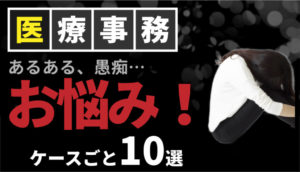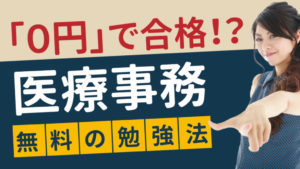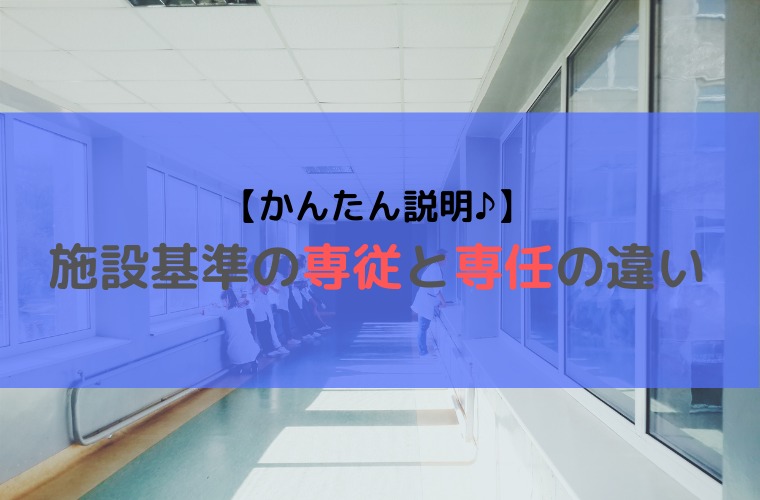にたような言葉で、調べても具体的な事例がなくて、わからない医療事務員さんも多いかと思います。
結論は、
基本的に専任・専従は【配置】に関係してのことを示しています。
例えば
回復期専従とかは、回復期の業務しかできない。
といった感じで、ざっくりいえば病棟などで働く場所の範囲を示しています。
本記事では、専従と専任には、若干の違いがありますので、そこらへんを簡単にまとめてみました。

施設基準における【専従とは】
その業務の専従として指定されてしまえば、指定された以外の業務は行ってはいけないということになります。
例えば
回復期専従とかは回復期の業務しかできないので、人でが足りないので一時的に一般病棟にヘルプに行ったりすることもできません。
もしヘルプに行く場合は、極端な話その都度に変更届け出を提出しなければいけません。
しかし、その都度に変更届を出すなんて面倒なことをすることなんてまずないので、基本的に『専従の人は、決められた業務しかできない』という認識していなければいけません。
施設基準における【専任とは】
例えば
回復期の専任であっても、人手が足りないときに一時的に一般病棟で業務を行うことができます。
他のところと”兼任できる”ポジションになります。
言ってしまえば、オールラウンダーな感じです。
なので、極端な話ではありますが…
回復期と一般と療養の3つを兼任することができます。

しかし、専任として届け出を出す場合には通常であれば、他と被らないようにするほうがよいでしょう。
兼任できると考えていても、明確にOKとはいいきれません。
厚生労働省の通知関係にもそういったことが書いてあるものを見つけられませんでした
できるだけ、配置の方法については、専従と同じ扱いで届け出ることをおすすめします。
めずらしい例
通常は【配置】に関しての指定なのですが【業務】に関しての専従とかを指定している施設基準もあります。
【業務】と【配置】とでは別々の事を示していることがあるんですね。
退院支援加算とかの施設基準は、そんな感じで記載されている部分があります。
参考までに下記リンクの“P7”に質問事項としてあります。
まとめ
だいぶ、ざっくりとした説明になりましたが、こんな専従と専任は
- 専従→指定された業務しかできない
- 専任→指定された業務以外も一応できる
こんな感じ、と覚えていればいいと思います。
大事なのは自分の担当する病棟などの、専従者と専任者ぐらいは把握しておくことだと思います。
専従と専任はなれるまでは、ごちゃごちゃするかもしれません。
また、職員が辞めたり移動になった場合にその都度、人員配置の変更を届け出変更しなければいけないので、自分の病院の職員の把握ぐらいはできたほうが有利かもしれません。
合わせて読みたい
当ブログでは医療事務の初心者向けに多数の記事もありますので参考にしていってください~