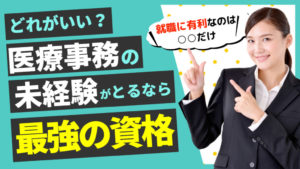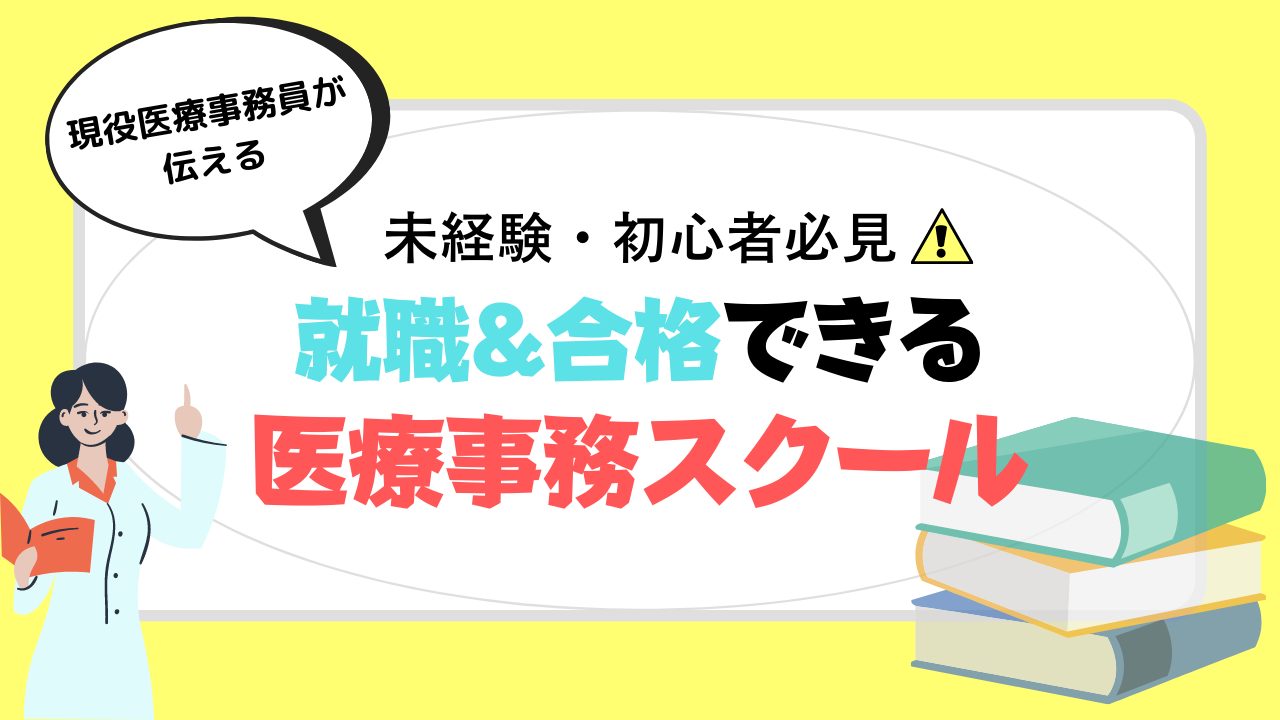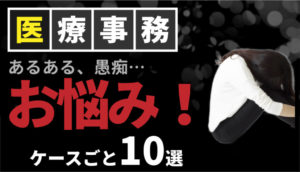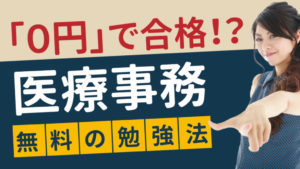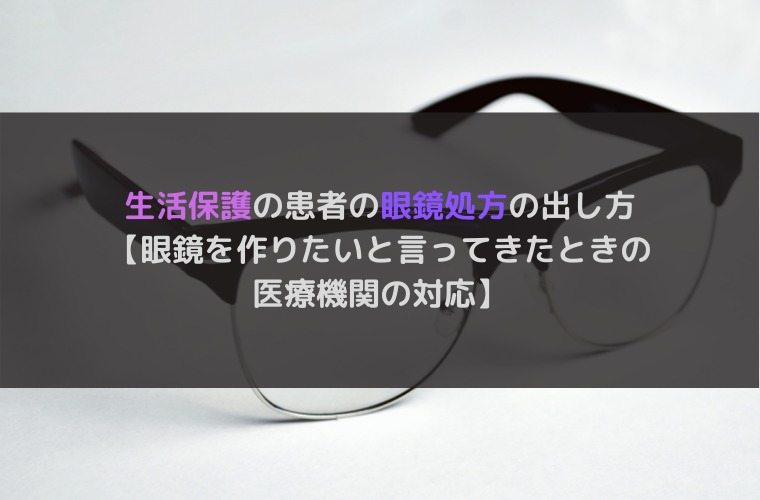意外と生活保護の方で眼鏡を作られる方って意外と多いですよね。眼鏡は生活必需品ですからね。
そんな生保の人が「眼鏡を作りたい」と申し出があった場合、医療機関は請求方法はどのようにしたらいいのでしょうか?
また、その作成までの流れはどんな感じになる?
本記事では、生保患者が眼鏡を作るときの対応と請求の流れをまとめています。
眼鏡処方の意見書の流れ
生活保護の患者で眼鏡を作るときの請求のポイントをまとめました。
まず最初に市役所へ連絡する
市役所(生保を管理してるとこ)への連絡 ※ここがなにより重要です。
眼鏡を作成するあたり、これに対して意見書が必要になります。その意見書は市役所が発行します。
通常は患者から市役所へ「眼鏡を作りたい」と連絡が行き、市役所から医療機関へ依頼がくるという流れになります。
(たまに、意見書を本人が直接病院に持ってくる場合もありますが、この場合も役所への確認が必要です。)
医療機関の対応は意見書の作成のみ
市役所から意見書が届いたら主治医に作成をしてもらいます。
必要箇所を記入後、市役所へ返送を行います。
医療機関の対応の流れとしては以上です。
やることは少ないですが、眼鏡の作成などな眼鏡屋さんへ行いますので、その後の対応は市役所と眼鏡屋さんになります。
患者さんの動きと病院の流れ
本来であれば、市役所と生活保護患者本人がやり取りや説明を受けて眼鏡を作成していきますが、たいていの場合はうまくっていません。
結局は医療事務側で説明や対応を求められることがほとんどです。
なので、そういった場合にも対応できるように、患者さんと医療機関でそれぞれ作成までの流れを別々でまとめました。
生保患者自身の流れ
step
1初診の場合は受診してもらう
当たり前ですが、基本的には診察が必要です。
大体は2回目以降の受診で眼鏡処方せんをだしてもらえるのではないでしょうか。
(私の勤務病院では2回目以降ですが各医療機関によってことなると思います)
step
2発行された処方箋は本人に渡してもよい
医療機関で作成した意見書を参考に市役所が眼鏡作成してOKか判断するので、それまで本人に大事に持っていてもらう。
step
3眼鏡作成は市役所からOKがでてから
市役所へ連絡し意見書を持っていく眼鏡屋を伝える
→市役所が眼鏡屋へ連絡する
→市役所が医療機関記入後の意見書を眼鏡屋送り見積もり欄を記入する。
※眼鏡処方せんの期限は1ヶ月だが、それに間に合うように役所も動いているようです。ただし意見書も早く記入し返送しないと期限があるので注意。
市役所の動きと医療事務の流れ
- 役所へ眼鏡を作る旨の連絡をする
-
役所より補装具の要否意見書が届くDrへ記載依頼
-
医療機関の意見書の部分だけを記入して役所へ返送
-
役所が意見書を見て眼鏡を作成してもよいか判断する
-
OKであれば役所から眼鏡屋へ連絡して意見書の見積もり書欄を記入してもらう
-
眼鏡作成
以上のような流れになります。
注意ポイント
意見書を作成時、見積もり金額は記入しない。眼鏡屋で記入します。
医療機関の対応としては以上です。
まとめ
本来は、医療機関としては意見書を書くぐらいしかすることないのですが、結局、医療機関側が干渉する(面倒みる)ケースが多いので流れをつくりました。
こんな感じなんだと思ってされもらえれば大丈夫なのではないかと思います。
見出し(全角15文字)
当ブログでは医療事務向けの情報を発信しています。このほかにもトップページから検索もできますのでご活用ください。