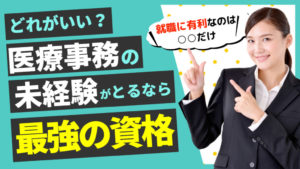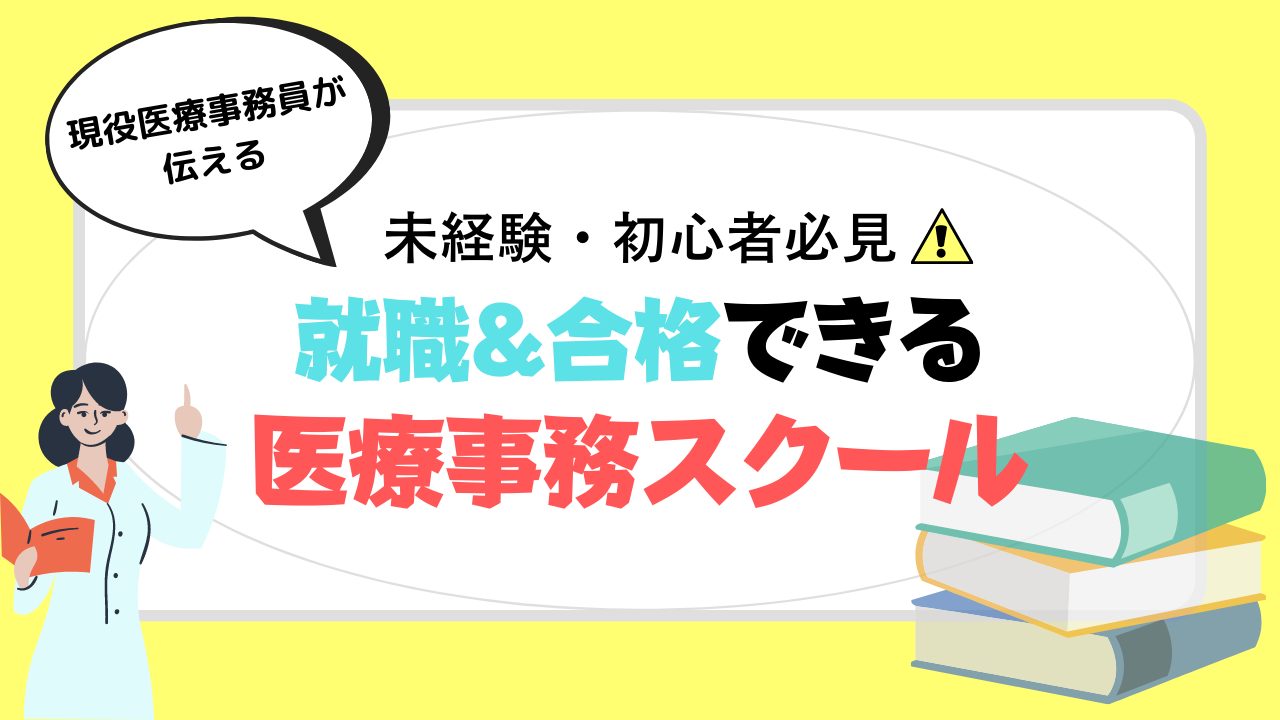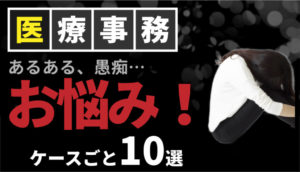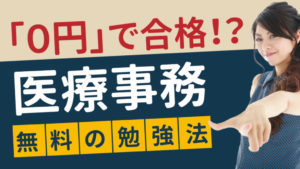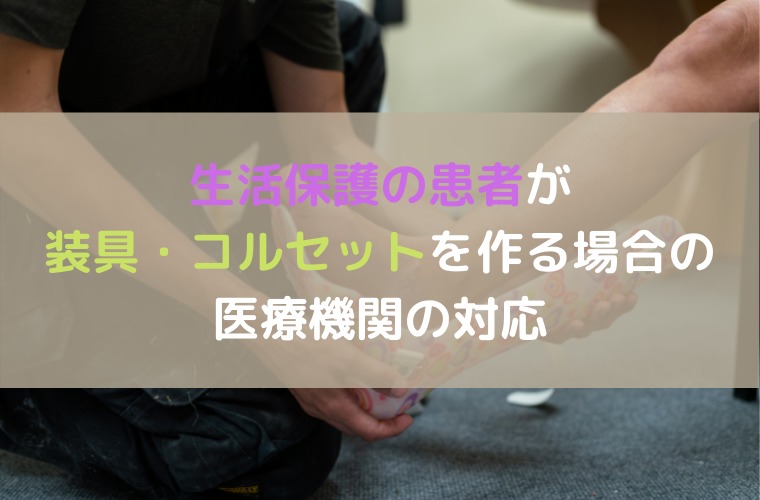結論、生活保護患者からは費用は徴収せず、生活保護の担当の市役所に意見書を提出するという流れになります。
そこらへんの詳しい内容を本記事ではまとめています。

※そもそも、装具の請求方法が分からないという人はコチラの記事から見たら理解が深まると思います。
まず最初に医療事務がすること
装具を作る前に、まずは市役所(生活保護の担当者)へ装具を作成する連絡をしましょう。
装具を作るという情報を得た段階で市役所も動き出すようなので、まずは情報を共有していきます。
ちなみに、生活保護患者本人から市役所へ連絡するという行為に期待はしない方がいいです…
ほとんどの生活保護患者はそこまで気にしていないので、医療事務側で管理してあげないとトラブルの元になります。
ポイント
事前に外来や相談員さんと連携して「生活保護の人が装具を作る際は事務に連絡してください」等の流れを作っておくと安心です。
装具作成までの流れ
- 市役所へ装具を作る旨を伝える
- 市役所から装具の意見書を郵送してもらう(本人が持ってくることもある)
- 意見書を主治医に依頼し記入・作成する
- 意見書を装具業者へ渡す
- 装具業者が見積りの項目を記入し直接、役所へ郵送してくれる。
- 本人へ『装具券』が届くらしい。それを装具業者が処理する。
というような流れになります。
医療機関側がすることとしては、意見書を作成して装具業者へ渡すという作業だけになります。
基本的に代金はすべて生保負担になるので本人の負担はありません。
とりあえず、これさえ分かれば一安心ですね。
作成時の注意点
病名に関してもなんでもよい、という訳ではない
例えば『圧迫骨折』等の緊急性のある病名だったらOKとか。
ただし、緊急性がなくても作成する連絡をしておけばだいたい大丈夫。トラブルは回避できます。
意見書の理由の項目
× 『予防』とかでは通らないことがあるらしい。
○ 『固定と安静』がよい
そこまで神経質になる必要なないですが、予防とかでは緊急性がないので申請が通らない可能性もあるようです。
できるなら、重々しい理由をつけるのがいいかもです。
意見書の作成後は市役所ではなく装具業者さんへ
意見書の記入後は市役所へ直接郵送するのではなく、装具業者さんへのお渡しになります。
装具業者さんが見積り金額を記入後、役所へ郵送という流れになります。
※私は直接、役所へ送ってしまったことがあり役所から「見積り金額がないですが…」と指摘を受けたことがあります。
ちなみに
市町村によって意見書の書式は違うと思いますが、私の地域の意見書では
主治医の署名欄は『院(所)長』になっているが
- 院長(ざばん)
- 記入した主治医の署名
どちらでもかまわないそうです。医師であれば問題ない。院長だったら確実らしいとのことでした。
まとめ
医療機関としては意見書を作るということぐらいなので、生保だからといって特別に面倒なことをするということはないです。
市役所への連絡さえしっかりしていれば問題はないと感じました。
生保の患者さんは流れなど手続き方法を理解していない人が多いので、医療事務側ですべて手続きした方がスムーズだと思うので本記事が参考になれば幸いです。
合わせて読みたい
当ブログでは医療事務向けに情報を多数発信しています。トップページからも検索ができますのでご活用ください~