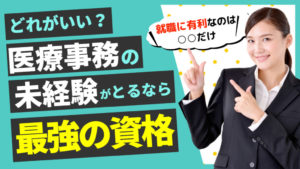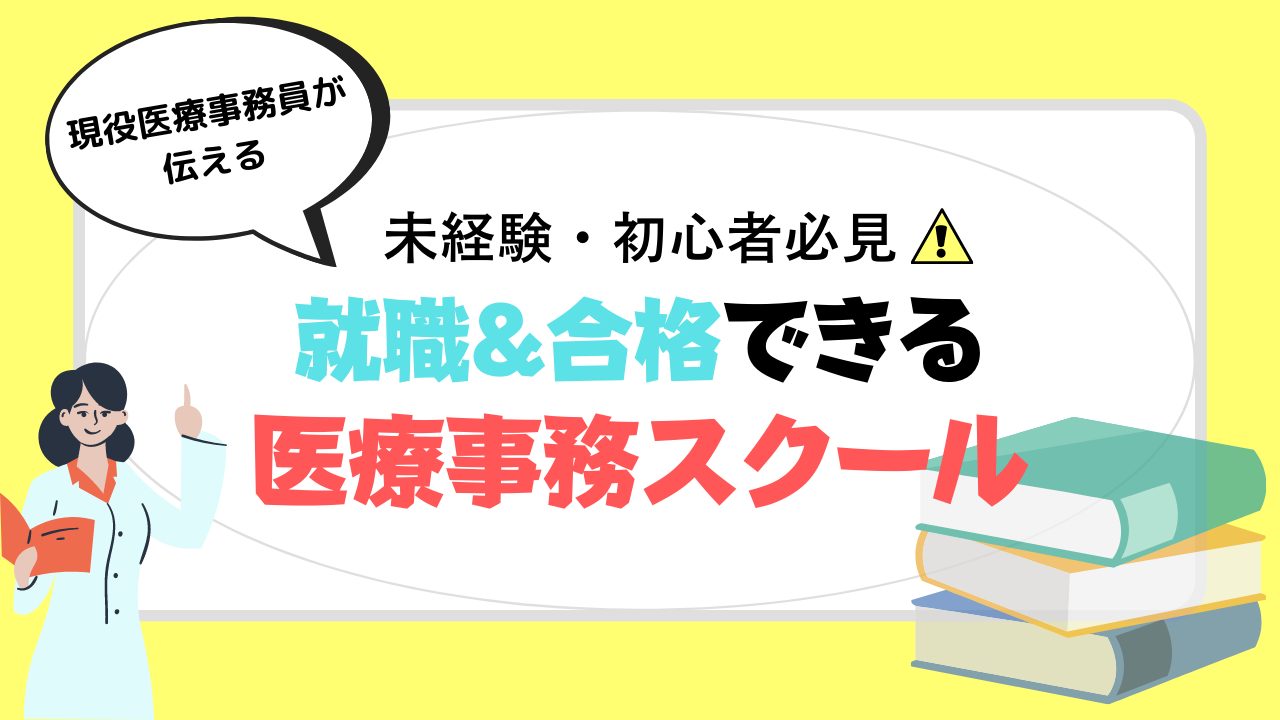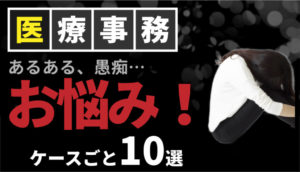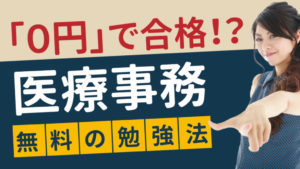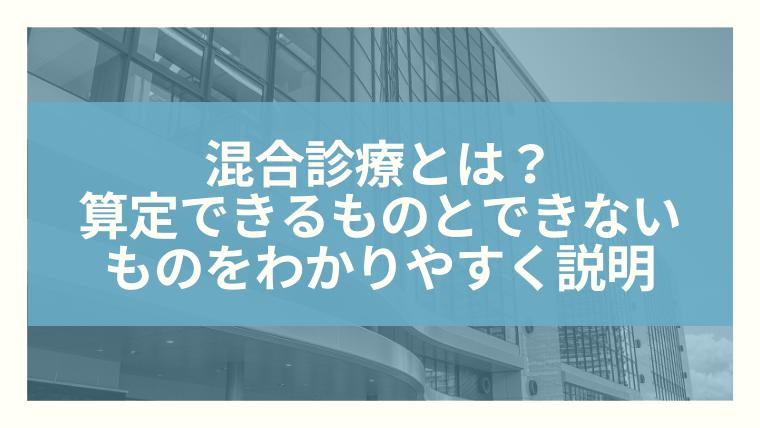という医療事務員さん向けの内容です。
混合診療については、早見表や青本の最初のほうのページに具体例などが合わせて記載されています。
ある程度の判断基準もそこで行えるかと。
本記事では、どうやって算定をするのか?ということもですが、混合診療の基本的な部分についても詳しく説明していきたいと思います。
混合診療とは
混合診療は「一連の診療の中に保険診療と保険診療外(自費診療)が混在する」ことを言います。
混合診療は、現在の保険診療を行うにあたって認められていません。
ちなみに、混合診療の禁止の理由として
- 安全性と有効性が確保されていないこと
- 患者の不当な負担を招くこと
- 患者の経済力の差が医療の差を招く恐れがあること
ということが挙げられます。
また、療養担当規則にも定められており
療養担当規則第18条(特殊療法等の禁止)
保険医は特殊な療法または新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほかは行ってはならない。
※「厚生労働大臣が定めるもの」とは 療養費の対象となる評価療養、選定療養のことを言います。
とされています。
そして同第5条において、 被保険者については、療養に関わる費用のうち一部負担金の他に、入院時の食事療養・生活療養に関わる標準負担額、評価療養選定療養に関わる特別の料金等の負担を求めることができる旨を限定的に上げており、これはそれ以外の負担を求めることができないことを意味しているとされています。
つまり、、、
保険診療を行う際に自費が発生するものについては、決められたものしか自費で徴収できないということです。
なんでもかんでも自費で徴収することができないということですね。
また、考え方の一つとしては、本来すべて自費になるものを一部だけ保険診療(国や市町村からだしている社会的な資源)で行い、自分勝手な都合で、それを合わせて利用する。
そうすることで、診察する費用(診察料等)は保険診療で請求すると、残りは自費(自分勝手な分)の治療、材料や機材の分の支払いだけになります。
つまり、保険適用できる分は自費で支払わなくて済むので、支払う額が少しお得になります。
これではムシが良すぎるのでは?ということです。
こういうケースを防ぐためにも、混合診療の禁止がされたのですね。
これはあくまで、個人的に例を挙げて説明しただけで、他にもさまざまな理由があります。
混合診療にあたるもの
保険診療中、治療目的で保険外の薬剤投与や検査を施行し、実費徴収を行う。
例えば、 注射が痛いのが嫌だから前もって痛み止めを投与する分のお薬代などです。
本来であれば治療に直接必要ないのに使用したものなどです。
言ってしまえば、患者さんの自己都合で使用されたものです。
国としては、本当に治療に必要な項目は、すべて保険請求の項目の中にあるという考えのもと動いています。だから、その項目にないものは全て自費扱いとなってしまうのでしょう。
また、一連の診療の中で、ある日は保険診療、別の日は自費診療をすることも該当します。
混合診療にならないもの
※実費徴収ができるもの
1.対象疾患の診療と関係ない検診の施行(入院中も含む)
特に多いのが健康診断などではないでしょうか。
2.対象疾患の診療と関係ない患者の希望による血液型の判定
3.予防接種の施行(入院中も含む)
4.生活改善のためのバイアグラ錠の処方
このバイアグラ錠の処方に関しては、当院でも結構ケースがあります。
結構算定の方法が面倒くさくなります。
このため(バイアグラ)だけの診察であれば、診察料と処方箋料の全てを自費で計算すれば良いのですが、定期処方(保険診療)と一緒に出した場合は入力が面倒です。
定期処方の分だけは保険入力、
バイアグラの分は、それとは別で再診料と処方箋料を自費で入力しなければいけません。
ここだけは注意しなければいけませんね。
混合診療についてのまとめ
混合診療についてまとめてみました。
とはいっても、青本の最初の方のページに混合診療に該当するかしないかの表が載っているので、そちらを参考にされた方がいいかもしれません。
とりあえず、患者さんのわがままだったり、自己都合で発生する診療・検査・投薬・物品の購入は混合診療にあたるかもしれないということを頭の片隅に入れてた方がいいでしょう。