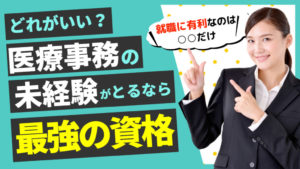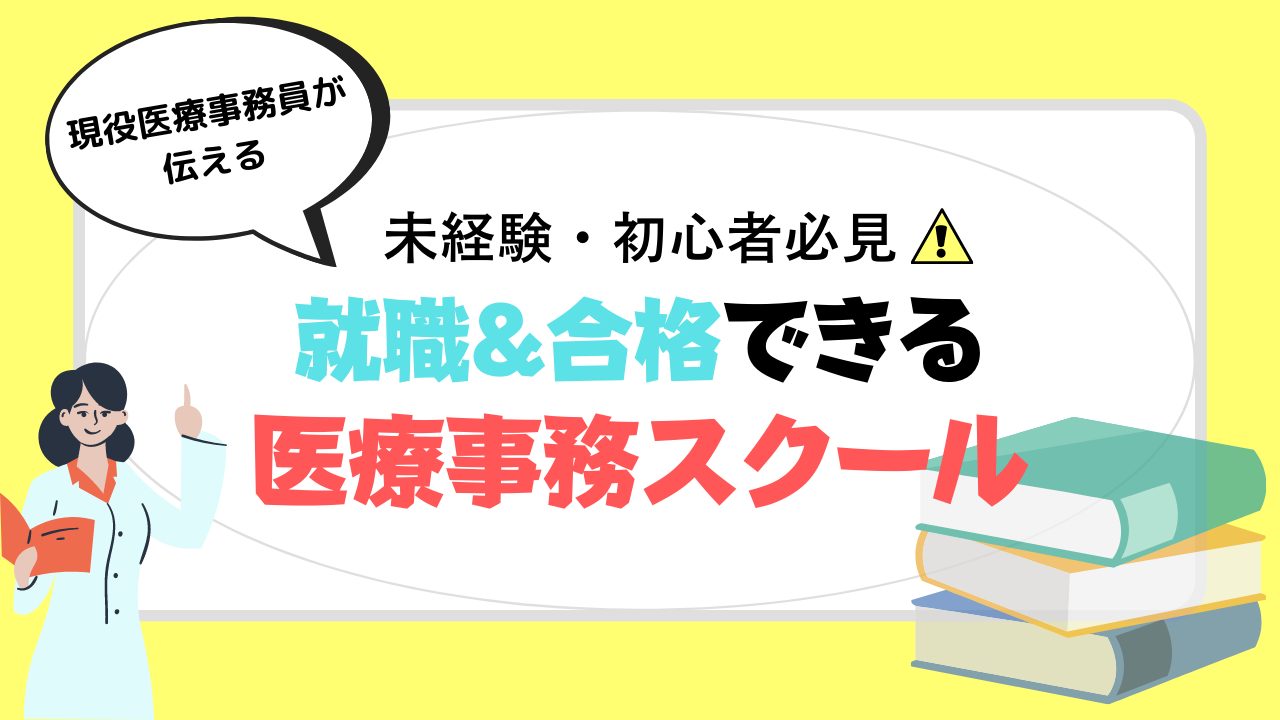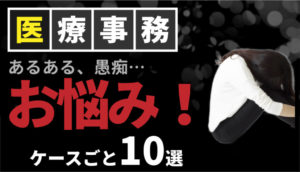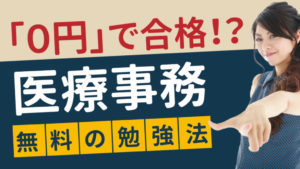と考えている医療事務員向けの内容です。
この記事では実際にFPの資格勉強をして合格した私が実体験をもとに
- 勉強して分かったこと
- FPのメリット
- 医療事務だからこそFPの勉強して分かったこと
を紹介していきます。
医療事務の資格ももちろんよいのですが、それ以外にも面白そうな資格はたくさんあります。
その中で、今回は医療事務以外の資格であるFP資格がオススメでした、そちらについて書いていきたいと思います。
最初にFPを勉強しようと思った理由
結婚・育児となると、どうしても切り離せないのがお金の話。
特に結婚してから急にお金の不安が付きまといます。
さらに、家族が一人増えるとなると話は別で一気にお金に対する将来の不安が増えました。
そういった不安(お金)の事を調べていくうちに、よく出てきたキーワードが”ファイナンシャルプランナー”でした。
気になり、本屋でテキストを調べていたら、自分お金がに対して考えていた
”自分が不安に思っていること”
”言葉は聞いたことあるけど、意味はわからなかったこと”
”ずっと気になっていたこと”
すべて載っていました。
しかも、3級からというお手ごろさ?
3級ぐらいなら楽勝かなと思い速攻でテキスト購入。
試験勉強へのやる気・モチベーションは下がらなかった!
飽き性の私ですが、とりあえずは勉強を始めることにしました。
勉強開始!!
・・・・・・・
・・・・・・
・・・・・
・・・
やっぱ明日からやろ・・・
とはなりませんでした!!
なぜなら、リアルタイムで気になっているお金の事で興味あるものばかりだから。楽しくテキストも読み進められます。
なぜに興味あるものだと飽きないのでしょうか。
やはり、一番は”自分に直接関係があるもの”だからでしょう。
自分に置き換えて考えると、真剣に物事を考えるものです。
試験結果
ファイナンシャルプランナー3級合格しました!
知識は増えましたが、経験(アウトプット)する機会が少なくせっかく習得した知識がどんどん頭から抜け落ちているような気はしますがw
せっかくなので、2級も受験してみようかと迷い中です。
FP3級/2級を取得する3つのメリット

メリット①:三大資金計画について意識できる
人生の三大支出は「老後・教育・住宅」です。
この3つをしっかり手当てできれば、生涯ゆとりある生活を送ることができます。
仮に、生涯賃金が2億4,000万円(平均年収600万円×40年)のサラリーマンがいたとします。
税金・社会保険料でざっくり25%取られるとすると、自由に使えるお金は1億8000万円です。
- 老後資金 約2,000万円
- 教育/養育費 約2,500万円(1人分)
- 住宅資金 約3,500万円

これを現役時代の40年で割ると、1年あたりの生活費は250万円になります。
なんと月あたり20万円ちょっとにしかなりません(養育費/住宅費込みでは30万円を超える)。
こういうことを、若いうちに理解しておくことは重要です。
要するに、「会社員は何も考えずに暮らしていたら、絶対にお金持ちにはなれない」という肌感を持っているかどうかということです。
こういう感覚を持っていないと、
- 老後資金は、つみたてNISAやiDeCoを利用して少ない資本で大きな額にする必要がある
- 住宅は、ハウスメーカーの口車に乗せられないようにしながら、中古住宅を賢く利用する必要がある(もちろん、お金より「夢のマイホーム」に価値を見出している人はお金をかける価値があります)
- 教育は、周りの雰囲気に流されずコスパの良い投資先を選定する必要がある
という話を聞いても、

FPを学ぶことで、人生の三大資金計画に対する意識が強くなることは間違いありません。
メリット②:無駄な保険に入らなくなる
FP学習の大きなメリットの1つとして、社会保険に詳しくなれるということがあります。
社会保険とは次の5つのことを言います。
- 医療保険
- 介護保険
- 年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
日本は、国民皆保険の制度を採用している先進国です。
民間の保険に入らずとも、十分な水準の保障を受けられるようになっています。
例えば、医療事務員はおなじみの高額療養費制度を使えば、月の医療費負担額は10万円以内におさまります。どれだけ医療費がかかろうと、必ずです。
たとえ入院・手術を1年間繰り返し、治療費の総額が1,000万円かかるような大病を患っても、

また、会社員だと病気やケガで働けなくなった時は傷病手当金が受けられます。最長で1年6ヶ月、働いていた時の給与の3分の2程度の給付金が受けられます。
このように、普段の通院だけでなく
- 医療で高額な治療費がかかった時
- 病気やケガで働けなくなった時
公的な保険で十分賄うことができるのです。
ところが、高校や大学ではこのようなことは学びません。
そのため、色々な民間保険に加入している人は、ほとんどのケースで「入りすぎ」になってしまっています。
- どのような状況になった時
- 公的な社会保険からどのような給付が受けられるか
ちゃんと把握した上で民間の保険に入っている人は、かなり少ないんじゃないでしょうか。
FPを学んだ人は、その後保険内容を自分で見直して保険料の適正化を図る人が多いです。
それだけFPで学ぶ社会保険の知識は役に立つということですね。

私も声を大にして言いたい。

メリット③:資産運用に関する基礎用語が身につく
FPを学習することで、資産運用に関する基礎知識がたくさん身につきます。
株式、債券、投資信託、外貨預金、ゴールド、デリバティブ、ポートフォリオ理論etc…
先に断っておくと、FPの知識を学んだからといって投資成績が良くなるということはありません。
FPで学ぶ知識は、あくまで基礎の基礎だからです。
しかし、基礎を学ぶことで大きく次の2つのメリットが得られます。
- 投資の向き・不向きが分かる
- より専門的な書籍が理解できるようになる
FPの知識にアレルギー反応がでるようなら、残念ながらあなたに投資には向いていないかも。
でもその一方で、もし、「FPの学習が楽しい!もっと知りたい!」と思うようであれば、投資家の適性があると言えるかと。
自己責任のもと、自分に合うリスクをとった投資ができるということですね。
もしそうなれば、より専門的な書籍を利用して、知識を深めていくのがオススメです。
いきなり専門書を読んでもちんぷんかんぷんでしょうが、FPレベルの知識を備えておけばかなりスムーズに読み進められると思います。

メリットまとめ:複利効果が働くので、若ければ若いほどお得!
学習・資産運用の世界では「複利」のパワーが働きます。
お金が雪だるま式に増えていくということです。
- 住宅資金は早いうちに準備を始めた方が良い
- 老後資金は早いうちに準備を始めた方が良い
- 教育資金は早いうちに準備を始めた方が良い
- 民間保険は必要最低限にし、余資は資産運用に回した方が良い
- マネーリテラシーは若いうちに身につけた方が良い
20歳~30歳である程度のマネーリテラシーを身につけていれば、その後の暮らしはグっと有利になるわけです。
FP試験は、今後の人生を経済的に楽にする良いきっかけになってくれるでしょう!

というわけで、次にFPの勉強方法について紹介します。
FPの勉強方法
めっちゃシンプルです。予備校はいっさい不要です。
独学でOK。これで合格できるかと。
- 市販のテキストと問題集を買う
- 問題集を2~3周やる
以上の通り。
FP試験は、試験傾向が安定しており難問・奇問がほとんどありません。勉強すれば必ず報われる試験です。
書店に売っている参考書を使えば間違いなく合格レベルに到達します。
それでも…

と感じている人はスクールも検討してもいいかもしれませんね。
FPの講座であればカリキャレなら無料の資料請求で申し込み前に事前にどういった内容か確認できるので安心です。

って人は一度、資料請求をしてモチベーションを上げてから勉強するのもいいかもしれませんね。
\無料の資料請求してみる/
私の勉強時間
ちなみに、まったく金融に関しては疎かった私でしたが、興味のある分野だったのでガッツリ勉強に集中することができました。
勉強時間にしてだいたい20時間ぐらいでしょうか。
テキストを一通り10時間ぐらいで読み込んでいき、残り半分を、過去問を解く時間にあてるといった感じでした。
過去問で大体の感触がつかめるので、問題集を買わなくても十分だと思います。
※過去問はネットから無料ダウンロードできる。
試験内容は過去問と、さほど変わりはないので、過去3回分の過去問を3回づつやれば十分といった感じです。
まとめ:自分に自信がついた
私は資格を取得を取得したことにより自分に自信が少しつきました。
これは社会人になって言うのはお恥ずかしいのですが、大真面目な話で勉強に対して“楽しい”とも思えるようにもなりました。

また、“自分は勉強したらできるんだ!!”という気持ちは大事で、次へのアクションに繋がる大きな一歩だと思いました。
これを機にいろいろな知識の習得のために、さまざまな資格取得の為に勉強していこう!!
というような考えも持つこともできました。
今の生活に不安を感じているなら一度、FPの勉強をしてみるのもいいですね。
\無料の資料請求してみる/
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
医療事務の勉強だけではなく、少し違った視野を広く持てる人が増えてくれたらいいな~
それではまた!