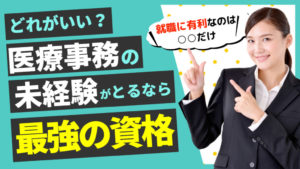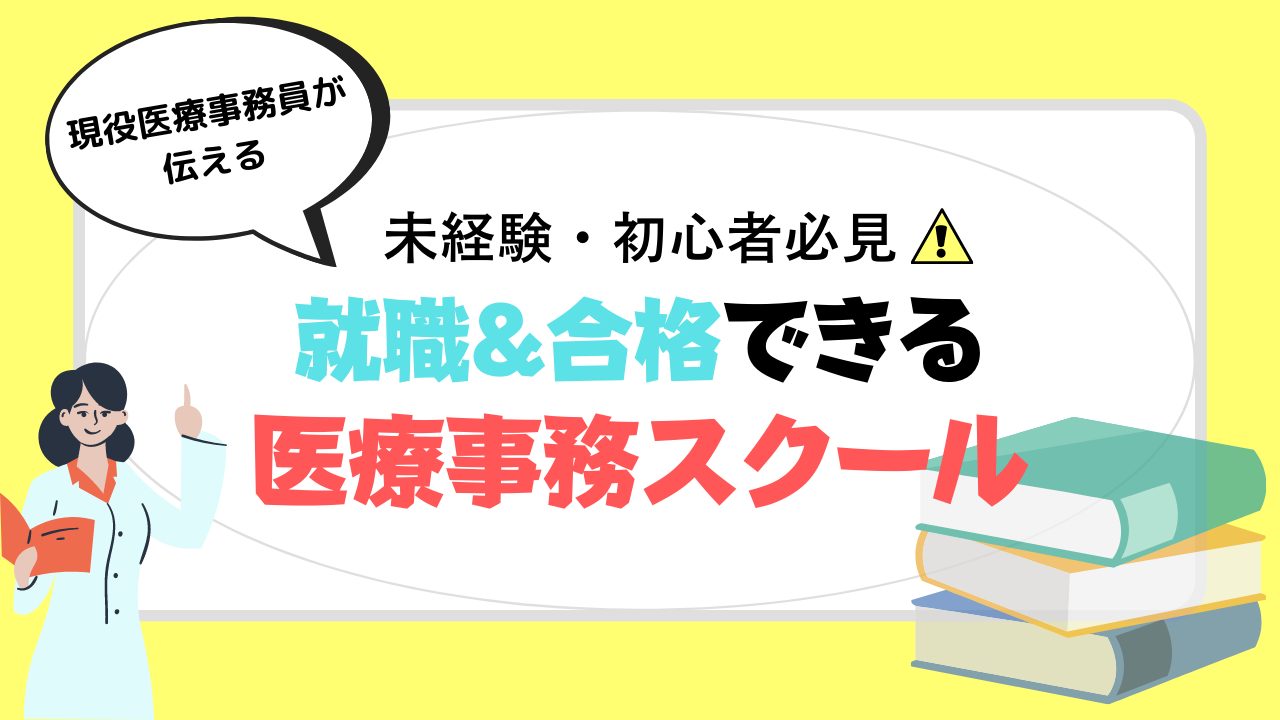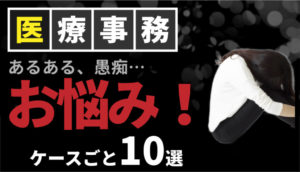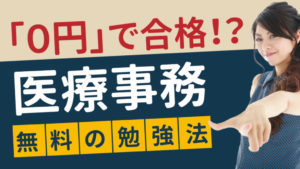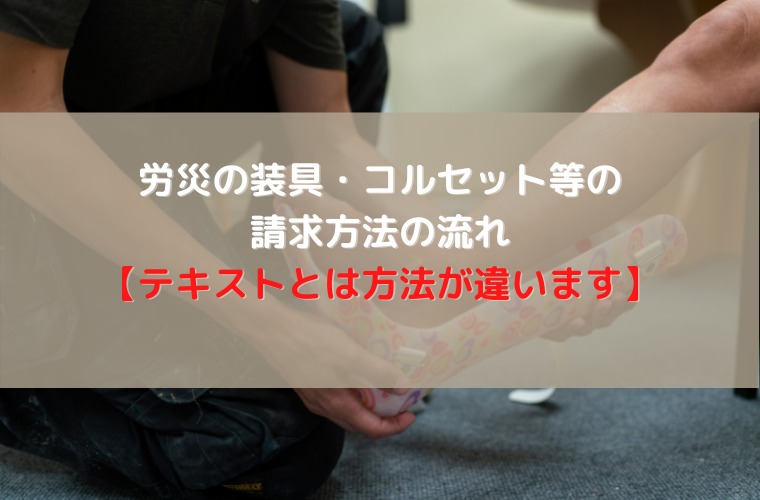労災の場合、健保請求とは請求方法が異なるのかもと混乱してしまいますよね。
ですが、結論から言うと
労災で装具を作っても、医療事務の請求の対応としては健保で装具費用を請求するのと同じ
になります。
今回、その請求の流れを説明していきます。

※音声動画のほうがいい~という方はコチラも参考にされてください♪
労災のテキストに載っている請求方法
先に重要な事をお伝えしておくと…

私の勤めている病院では、だいたい初診から3か月ぐらいの間に初めて装具をつくるケースが多いです。
このようなケースの場合は
労災のテキストの流れとは請求方法が異なってきます。
通常、労災のテキストに載っている流れ
※ここは読み飛ばしてもOK
- 申請者:労働局へ『義肢等補装具購入・修理費用支給申請書』を提出
- 労働局:労働局において内容の審査 申請者の診療担当医医療機関に対して症状照会を実施
※症状照会する項目
コンタクトレンズ、ストマ用装具、浣腸器付排便剤、重度障害者用意思伝達装置 - 労働局:労働局長から申請者に『義肢等補装具購入・修理費用支給承諾決定通知書』を送付
- 申請者:義肢等補装具業者に義肢等補装具の購入(修理)の注文を行う 義肢採型指導医において採型指導を実施
※採型指導を実施する項目
義肢、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車いす、電動車いす - 装具業者:義肢等補装具業者が、申請者に義肢等補装具を引き渡す
だいたい以上のような流れで、テキストは書いてあると思います。
装具引き渡しまでの流れは以上です。
【費用の精算】患者が費用を負担しない場合
患者さんが装具等の費用を負担せずに受給する方法は下記のようになります。
※ここもテキストと同じなので読み飛ばしてもOK
- 申請者:費用請求書に必要事項(受領任意の手続き等)を記入する
- 申請者:義肢等補装具業者に費用請求書等を渡す
- 装具業者:義肢等補装具業者が労働局に費用請求書等を提出
- 労働局:労働局長が義肢等補装具業者に費用を支払う。
以上になります。
これで患者から費用を徴収することはなくなります。患者さんからしたらこちらのほうが助かりますよね。
【費用の精算】患者が費用を負担する場合
患者さんが装具の費用を一旦、負担する方法は下記のようになります。
※ここもテキストと同じなので読み飛ばしてもOK
- 装具業者:義肢等補装具業者が申請者に費用を請求
- 申請者:義肢等補装具業者に費用を支払う
- 申請者:労働局長に費用請求書等を提出
- 労働局:労働局長が申請者に費用を支払う
上記で説明した方法が、労働局やRICから支給されている手引きなどにも記載があるような流れになります。
医療事務が実務で労災で装具(コルセット)を請求する方法
上記ではテキストに沿った請求方法について書いてあります。
しかし、今回伝えたいのは、あくまで医療事務員が実務での使用頻度が多いであろう請求方法についてです。

装具ができたら装具の費用の全額を患者さんから徴収する
装具ができたら医療機関側の対応としては、労災患者さんから直接費用を自費で請求します。
理由としては…
仕事中のケガで病院受診をしても、最初の段階では労災と認定されているか未確定のためです。
通常、最初に労災の患者さんが来た段階で『5号用紙』を提出てもらうと思います。
このとき、5号用紙というのは患者もしくは勤め先の会社が作成すればできます。
これは、あくまで会社が独自の判断で労災と判断したことです。
5号用紙を持ってきた、あるいは仕事中のケガだからといって必ず労災認定されるとは限りません。
なぜなら
最終的に労災と認定するのは労働局だからです。
まだ、労災と認定もされていないのに、労働局も装具の申請に対して許可することもできません。
なお、労災に認定されたどうかは医療機関も装具業者さんもリアルタイムで把握できるところではありません。
あくまで本人もしくは会社と労働基準監督署の間でのやりとりになります。
病院が労災として治療費を請求できる定義
以上の理由から、受傷後、短期間で装具を作る場合はテキストの流れと異なってくるということです。
装具代を患者本人が支払った後の流れ
- 業務災害の場合 『様式第7号用紙』療養補償給付たる療養の費用請求書
OR
- 通勤災害の場合 『様式第16号の5(1)』療養補償給付たる療養の費用請求書
上記を作成します。
これらの書類は、

通院にかかった交通費なんかも、この書類で払い戻しを受けることができるので病院がよく作成しますよね。
この書類を作成して労働局へ提出することで、全額支払った装具の費用が患者さんへ戻ってくるというシステムです。
アドバイス
ちなみに、この書類(7号様式)の医療機関で証明する項目で期間を証明する項目がありますが、この部分は、装具のオーダー日から装着の日付でいいようです。病院によっては、初診から装着の月の末日で記入しているところもあるようです。
参考記事 7号様式とかわからないという方はコチラから
患者さんが装具代全額を支払えない場合
装具は全額支払うとなると、何十万になったりと高額になるケースがでてきます。
中には支払えない患者さんもでできます。
もし、そうなった場合に下記のような方法もあります。
会社が立て替える
患者の勤務先の会社が立て替えるケースもあるようです。
会社が支払う場合は『受任者支払い申請書』を提出する必要があります。
ただし、立て替えができる企業は限られています。
月に労災保険料を100万円ぐらい納めている大企業でないと審査が通らないようです。中小企業の場合は適応されないので、やはり患者本人に支払ってもらうしかありません。
しかし、どっちにしてもお金は全額もどってくるので、そこは勤め先の会社と相談して立て替え(労災とかではなく個人間で)てもらうという手もあるようです。
私の経験談
小さい会社で良心的な社長は建て替えをしてることが結構あります。
このときの『様式第7号用紙』の振り込み口座の項目は、患者本人にするか、会社の口座にするかは労基に要相談でした。
なぜ、テキストと違う流れになるのか
労災に認定されるのに時間がかかるということもありますが、テキストに載っているのは治療後も慢性的に装具が必要な場合の手順になっています。
しかし、ほとんどの患者さんは治療初期の1回だけしか装具を作りません。
初期段階では、労災になるのか?ならないのか?は医療機関ではハッキリわからないので
分からないなら確実に費用は回収しておこう
という考えからです。
ちょっと乱暴な対応かもしれませんが、これで費用の取りこぼしもなくなるはずです。
まとめ:労災の装具費用の件で困ったら装具業者に相談してみる
装具業者さんも、せっかく作った装具の費用がもらえなくなるとなると大変です。
そこら辺を踏まえて医療機関と連携は取ってもらえると思います。
なので、迷ったら一度は装具業者さんに相談するといいかもしれませんね。
ネットや参考書に載っている内容とは少し違うかなと思いますが、完全に医療事務の立場から解説していきました。
医療機関によって対応は様々だと思います。
また、労災でも患者さんによって状況が違っていたりして対応が異なってくるかもしれませんが、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
あわせて読みたい
当ブログでは医療事務向けの情報を発信しています。関連記事もありますので参考までにどうぞ♪