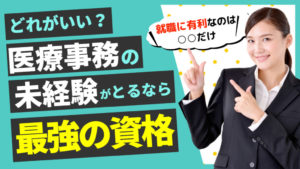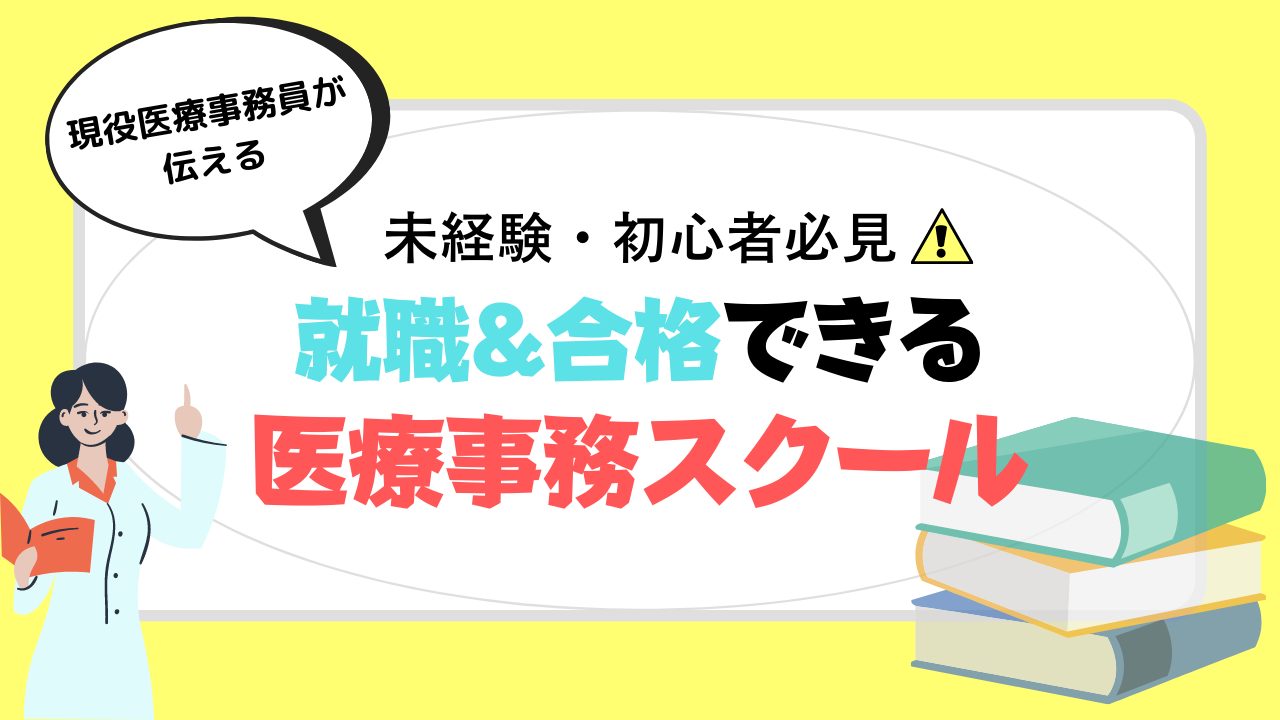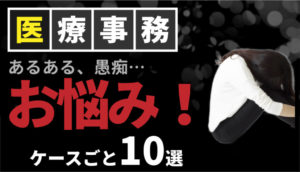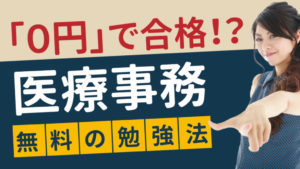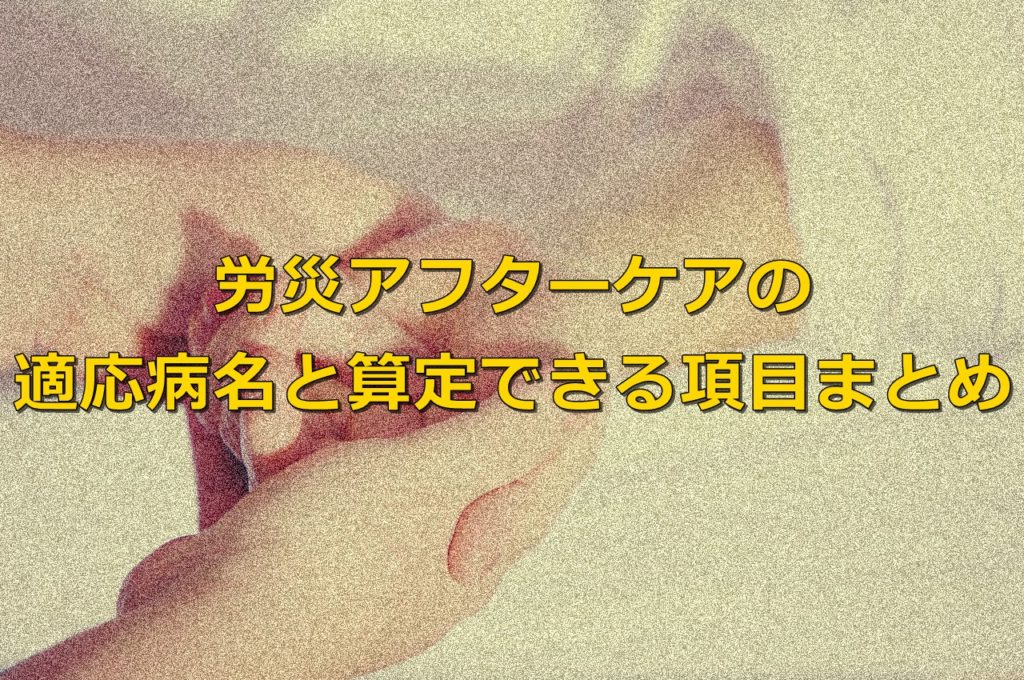労災アフターケアで受診をされる方の算定方法について、最初のうちは普通の労災と混乱することがあるんじゃないかと思います。
また、意外と勘違いしている事、間違っている事もあったりまします。
アフターケアは病名によって算定できるものが決まっていたりと、通常の労災と違い制限がたくさんあります。
なぜ、アフターケアは普通の労災と違い、算定できる項目が少なく制限も多いのでしょうか。
本記事では、アフターケアの適応病名と算定方法について医療事務員向けに書いていきます。
アフターケアとは
労災による療養を受ける者が、治ゆ(症状固定)した後において、
- 疼痛、痺れ等の原傷病と関連のある後遺症状を残す場合
- 症状固定時の症状を悪化させない又は維持するための措置を必要とする場合
- 傷病の特殊性から、症状固定後において再発する可能性が高く、定期的に検査等を行う必要がある場合
に、予防その他の保健上の措置(原則治療行為は含まない)として実施するものである
上記のような事が厚生労働省のホームページに載っています。
アフターケアの認識として重要なことは、上記にも黄色マーカーしている、予防その他の保健上の措置(原則治療行為は含まない)という部分になります。
算定できる項目について
上記はどういうことかというと、アフターケアは決められた診察料、投薬、検査しか算定できないのです。
例えば、普通の労災のように、「この検査は、労災の病名と関連あるから労災で算定しよう」
ということができないのです!!
すべての算定項目は決められており、医療機関ごとに判断して算定することはできません。
繰り返しになりますが、アフターケアは治療ではなく、症状固定後のフォロー(ケア)なんです。
ここの認識が大事になってきます。
入院中の算定について
もしアフターケア受給中の患者が入院した、算定はどうなるのでしょうか?
当然ですが、入院料は労災アフターケアとしては算定できません。
そもそもが、アフターケアでは治療を行わないので、アフターケアで入院することは、まずありえません。
ここら辺は、留意していたほうがよいでしょう。
アフターケア以外の病名で入院することはあります!
入院中にアフターケアの薬剤が出た場合
入院料は算定できませんが、それでも入院中にアフターケア対象の薬剤が処方されることがあります。
このときは、どうなるのかというと、薬剤料のみ算定することができます。
ただし、院内処方としての取り扱いとなります←入院中なので、外来として取り扱うのは少しおかしいですが、例外として。
健保のレセプトとは別で、アフターケアのレセプトで薬剤料のみを請求するかたちになります。(当然、再診料等は算定できません。)
ここでアフターケアのレセプトに、入院中である旨を記載しておかなければいけません。
例:「入院中のため、アフターケア対象の薬剤のみを算定しています。」的な感じです。
労災アフターケアと労災の考え方
労災と労災アフターケアは、どっちも”労災”とつくので、同じような認識を持っているかもしれませんが、内容はだいぶ異なります。
- 労災 ⇒ 労災に関連するものはすべて労災で算定していく
- アフターケア ⇒ 決められた(指定された)項目のみを算定していく
といった具合に覚えておくとわかりやすかもしれません。
両方を正しく理解していくことが、今後、正しい請求方法につながっていくと思います。