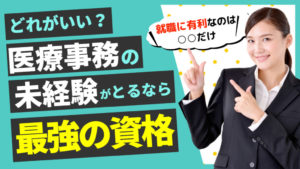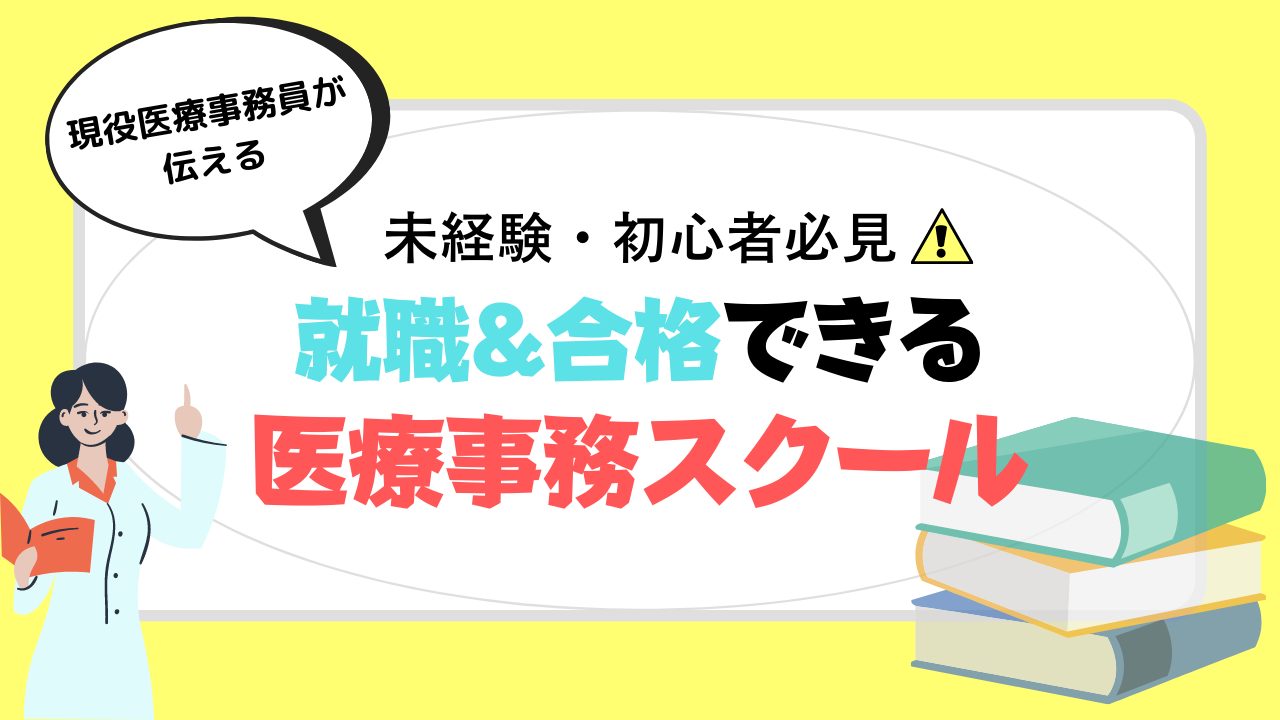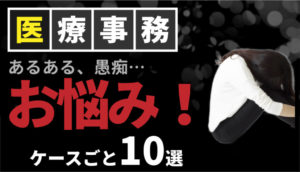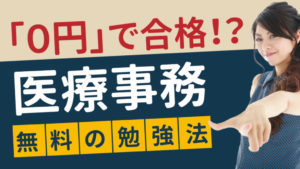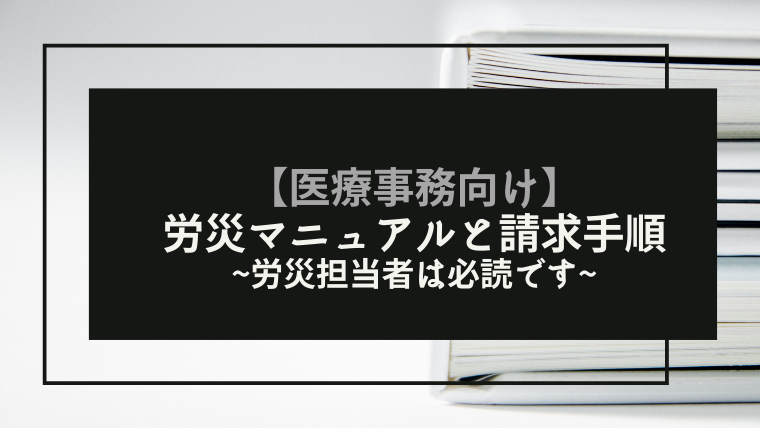「労災の請求業務をやったことがないので全く請求の流れが理解できない。」
「前任者が急にやめてまともな引継ぎもできてないので途方にくれている…」
なんていう状況の医療事務員もいるかもしれません。
初めて労災を担当するとか、労災の前例がない医療機関とかいろんなケースがあると思います。
本記事では、医療事務員さん向けに、少しでも労災の請求の基本的な流れが分かるようまとめてみました。
全ての医療機関に当てはまるというわけではありませんが、だいたいの流れとしてはこんな感じだと思います。

※音声や動画の方がいいという方は動画でも解説しています。
▼YouTubeはコチラ▼
労災患者への初期対応
労災患者さんの場合、健保請求ではないので、事前に本当に労災として請求ができるのか?といった確認が必要になってきます。
でないと治療費が請求できなくなってしまい、最悪の場合、未収になってしまう事もあります。
初期対応は結構重要。最初が肝心です。

初期対応①:患者の事業所の会社名・電話番号・担当者を確認
仕事中のケガというのは突発的なものです。
実際にケガをしてから『これは大変だ!病院に行かなければ!』となって慌てて病院を受診するわけです。
なので、ケガをした直後に病院に来た段階では、今回のケガを労災として取り扱うのか?ということを患者さんと会社側で話をまだ行っていない、なんてケースはよくあります。
考えるポイント
仕事中のケガは労災というのは当たり前ですが、初診の段階では労災だと証明できるものがないんですね。
もしかしたら、勤務中だったけど仕事とは関係ない事でケガをしたというケースも考えられるわけです。
労災と判断するべき根拠となる考えかたの記事はこちらから
労災になるかどうかはっきりしない場合、治療費は自費でもらっておくというのは常套手段です。
しかし、、、
ケガも突然のことなので、お金を持っていない患者さんが多いのも事実です。
とはいえ、後から治療費を支払いに来てくださいねと言っても、未払いのままトンズラされる…
なんて可能性もあるし、初診患者であればより疑わしさがでてきます。
では、どうするのがいいかと言うと患者さんの勤め先を確認しておくと安心です。
チェックリスト
- 会社名
- 電話番号
- 会社の担当者の名前
これら3つを確認しておいたほうがよいでしょう。
できれば、患者の同意を得て保険証、免許証など身分証明書のコピーをとっておくと安心です。

ここまですれば、音信不通になる…、なんてことにはならないはずです。
初期対応②:通勤途中の事故ではなかったか確認
すべてが”労災=仕事中のケガ”というわけではありせん。
通勤途中(交通事故)の場合は下記のどちらになるか確認をします。
通勤災害 OR 自賠責
通常、自賠責が優先されるが過失の割合等で変わってきます。
ここら辺の判断は、患者本人は良く分かっていないことが多いです…
もし、請求方法が明確ではない、ケガの発生状況がいまいち正確さに欠けるということであれば、患者の任意の自動車保険会社へ確認をとることが望ましいです。
理由としては、

確認後、保険会社から患者本人へ連絡が行くといった流れがベターです。
初期対応時の注意点4つ
ここまでの初期対応を説明してきましたが、次に、注意すべき点を解説していきますね。
初期対応の注意点①:仕事中のケガっぽいのに『労災じゃない』と言ってきたら…
結構多いのが、患者さんが会社に気を使って
「仕事中じゃない」
「労災は使わないです」
っていうパターン。
こういった場合は、
基本的に、労災の場合は保険証は使えない、自費になる可能性があることを伝えましょう。
そして、本人もしくは会社から労働基準監督署に、仕事中にケガして受診した連絡をするように伝えてください。
医療機関が労災隠しをしていないという事実が大事です。

初期対応の注意点②:国保の人も労災適応になる場合がある
個人事業主、いわゆる一人親方などの国保加入の方は仕事中のケガでも保険証を使った保険請求ができます。
というか、労災ではなく保険証を使用することになります。
ただし、任意の労災に加入、元請けの会社がかけている労災などで対応できるケースもあるので確認が必要です。
詳しい記事はこちらから
初期対応の注意点③:公務員の場合は労災は使えない
公務員は労災は使えません。
- 学校の先生
- 市役所、役場の職員
- 消防署職員
などなど…
こういった地方公務員は公務災害になります。
公務災害の場合は請求方法が労災とは全く異なるため注意が必要です!
公務災害の請求方法について過去の動画でも解説しています。
実際の請求方法の事例はこちら
初期対応の注意点④:労災に必要な書類を持ってきてもらう
次に請求に必要な書類についてです。
これは必ず必要なので、絶対に持ってきてもらってくださいね。
- ケガしてまったくの初診時 5号様式 OR 16号の3
- 他院からの転院時 6号様式 OR 16号の4

注意ポイント
あと、転院時に関しては、本来であれは16号の3が必要なのに間違って5号様式を持ってくることがあるので注意が必要です。
労災の算定から請求までの流れ
次に、算定入力から、実際に労基へレセプト請求するまでの流れをまとめました。
労災請求の流れ①:算定もれがないか入力の確認
労災は患者の負担金がないので、リアルタイムで計算してお金をもらうといういうことはありませんが、それでもレセプト請求時に算定漏れがあったりすることもあると思いますので注意が必要です。
ここでは、一般的に算定する機会が多いものだけを紹介していきますね。
初診時
まず、初診時に絶対に算定するべきものは2つです。
療養の給付請求書取扱料(5号用紙or16用紙)
医療機関が労災レセプトを請求する際に、絶対に必要なものです。
救急医療管理加算
初診から入院は7日分、外来は1日分のみ算定できます。
※転院時は算定できません。
この二つについては絶対に算定できるか確認をしましょう。
※救急医療管理加算については、点数が高いので要注意です。
再診時
次に継続して診察している患者、再診時に算定できるものです。
休業証明(8号様式作成時)
患者さんから記入依頼があるたびに算定できます。
1か月単位でかかっている患者さんは必ずといっていいほど持ってきますので、必ず算定するようにしましょう。
再診時療養指導管理料
外来患者に対 して再診時に療養上の指導したら算定できるとあるので、基本的には診察の都度、算定できると考えていいのではと思っています。
また、帳票を作成するなど記録を残しておくと安心かと思われます。
リハビリ、処置及び手術の四肢加算
労災で処置や手術を四肢(手足)に行った場合、労災独自のもので四肢加算が算定できます。
通常の保険請求よりも加算分が多く請求できますよね。
リハビリや処置は継続して行っていく事が多いので算定漏れをすると点数が大きくなってしまいます。
ADL加算
算定条件はありますが、入院でリハビリを提供している医療機関であればだいたい算定できるのではないでしょうか。
労災請求の流れ②:リハビリをしている場合は労災リハ評価計画書の作成
労災請求の場合も、リハ期限を越えてリハビリを実施する患者で、月13単位を超えて請求する場合はリハビリ継続の必要性のコメントが必要になります。
健保請求のように、計画書で対応していくことで管理もしやすくなります。
労災リハ計画書の書式は、手引きなどにも載っているので参考にされるとよいです。
ちなみに、電子請求の場合は症状詳記への記載でも大丈夫です。
電子請求のときは詳記の中に入れ込むので、別で紙媒体で作成して提出する必要はありません。
リハ計画書に関して、ほぼ健保請求と流れは同じという考えでOKです。
労災請求の流れ③:『新継再別』項目の医事コンの登録変更
例えば
先月、初診から月をまたいで継続加療している人は医事コンの継続区分を
『初診』→『継続』等へ変更しなければいけません。
例えば、1月は『初診』、2月は『継続』とレセプトに上がるようにしないといけないということです。
たまに、次の月も初診のままになっていることがあります。
これは医事コンに依存するところですが、今はどこの医療機関も医事コン使って請求してると思うので注意が必要です。
労災請求の流れ④:紙媒体を翌8~9日までに郵送する
労災5号様式(様式第16号の3)の提出は、
診療月の翌月の10日必着(10日が土日祝の場合は休日の翌日)
です。
電子請求を行っている医療機関であっても、5号用紙や16号用紙といった紙媒体のものは電子とは別で紙媒体として郵送しなければいけません。
紙媒体の郵送がどうしても10日に間に合わない場合で1日、2日ぐらい遅れそうなときは、事前に労災補償課へ連絡することをオススメします。
私の失敗例
私が過去に、9日の夜に郵便を出したことがあったのですが、到着が10日に間に合っていなかったようで、月遅れになってしまったことがあります。
郵送する書類
- 5号用紙や16号用紙など当院初診時に提出してもらう書類
- アフターケアのレセプト一式(請求するアフターレセがある場合)
労災請求の流れ⑤:電子レセプト請求
短期・長期は電子レセプト請求を行います。
これは通常の健保を電子請求する流れと同じ感じです。
ちなみに、アフターケアも現在は電子請求に対応しているようです。
まだまだあります!レセプト作成時の注意点
ここまで請求の流れや注意点を説明してきましたが、実はまだまだレセプトでは、注意するべき点があるので紹介していきます。

私病は労災レセプトにがらないように医事コンで病名を分けておく
労災の傷病名と私病は必ず分けて請求してください。
でないと、確実に労基から指摘が入ります。
「これって労災と関連ありますか?」
みたいな感じです。
例えば
患者さんが労災で受診したついでに『実は労災前からここも痛かったから薬を出してほしい』と、労災と関係ない事で薬をもらっていることもあります。
なので、本当に労災として請求できるのか?という見極めも大事です。
請求前に事前に主治医に確認しておくことをお勧めします。
労災病名と関連なさそうと判断されそうなものにはコメントをつけておく
例えば、骨塩定量などは労災の治療のために行うことがあったりします。
しかし労災病名には直接関係はないと判断されてしまうため、必要性のコメントつけないと労働局から問い合わせがくることがあります。
そうならないためにも、事前に必要性のコメントを
『こういった理由で、労災病名が起因して、こういった治療を行っていますよ~』
とつけておくと安心です。
労災発症から後日に『便秘』『逆流性食道炎』等がついたら”続発性”をつける
労災の直接のケガではないけど、関連して発症した病名に対しても注意が必要です。
必ず「続発性」とつけるようにしましょう。
例えば
- 便秘症 ⇒ 続発性便秘症
- 逆流性食道炎 ⇒ 続発性逆流性食道炎
こういった細かいところも突っ込まれることが多いので見落とさないようにしましょう。
紹介状が出た場合、紹介先の医療機関名をレセに記載する
これも結構突っ込まれることが多い。
ちなみに、手引きには一切そんなこと書いていないです。地域差があるのでしょうか?
最後に症状固定について
交通事故などと同じで労災の症状固定時(治療の終了時期)は患者さんとのトラブルにつながりやすいです。
必ず、主治医と患者本人に確認してからの症状固定が望ましいです。
症状固定について詳しくまとめた記事はこちらから
以上が、労災のルーティン業務の中で発生する割合が多そうなものだけをピックアップしました。

まとめ:最悪、労災のレセプト請求に必要な書類さえあれば請求できる
労災の初期対応や請求方法は覚えてしまえば、ここまでで説明したものと同じ作業なので、そこまで難しくはないと思います。
個人的に一番大変なのは、患者さんや会社が労災のレセプト請求に必要な書類を持ってこないときです。
何度電話しても持ってこない。もしくは『社労士に全て任せてるから~』とかいって対応しないところとか…
入院費とかになると、月遅れにするだけで月100万円単位で医療費が病院に入ってこなくなるのでヒヤヒヤものです。
月遅れにはならないように、労災のレセプト請求に必要な書類の提出の確認だけは早めがいいかと思います。
そういった一つの作業の確認で未収対策にもつながってきますからね。
通常の健保請求とは違い、ちょっと特殊な請求や対応で面倒くさいですが、慣れてしまえばルーティンなので、ひたすら経験して覚えていくことで自分の力になってくると思います。
今回の記事が医療事務員さんの参考に少しでも参考になれば幸いです。
質問はブログの問い合わせフォームやTwitter(@5nenme_iji)でも受け付けていますので気軽に問い合わせしてくださいね~
他に参考になりそうな労災関係記事をまとめましたので、よろしければこちらもご覧ください