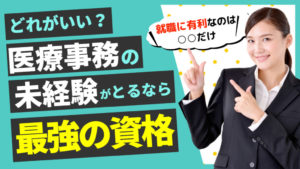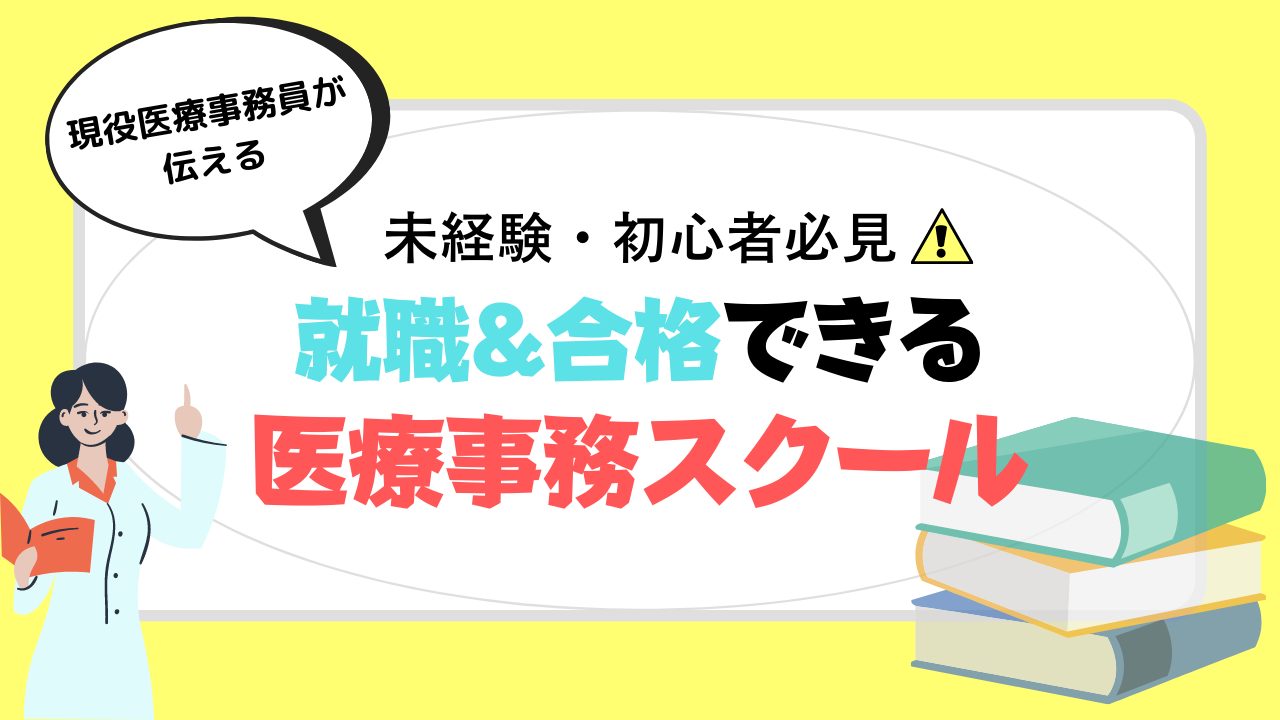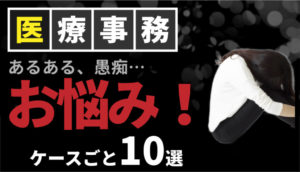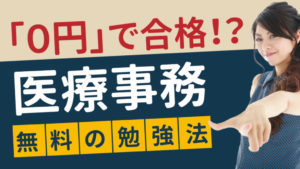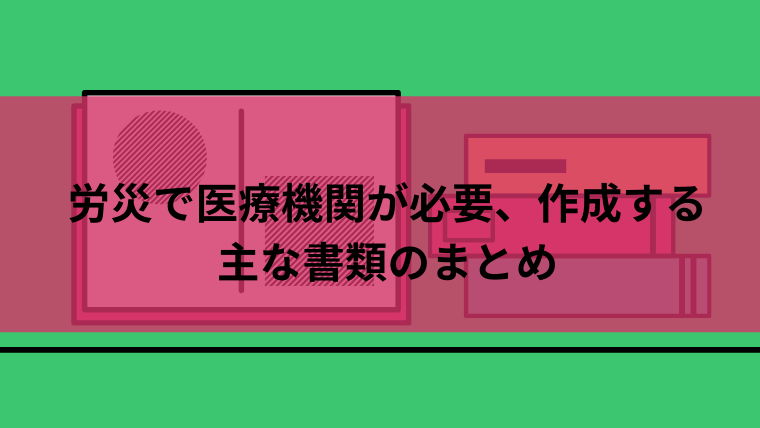労災患者の場合、医療機関に提出する労災関係の必要書類って多いですよね。
業務災害なのか、通勤災害なのか、この違いによっても提出書類の種類が異なってきます。
また、それ以外にも、患者さんが定期的に休業補償のために持ってくる書類などもあります。
医療事務として始め、または労災担当になったばかりの時は、種類が多くて混乱してしまうこともあると思うので、本記事では医療機関(医療事務員)が労災で使用する関係書類についてまとめました。

業務災害の場合
様式第5号
仕事中に受傷し、労災指定病院で治療を受ける際、労災指定病院に提出する書類です。
労災である事を証明する書類であり、医療機関はこれをもって労災として治療費を労働局に請求することができます。
この用紙は初回レセプトに添付、郵送をおこないます。(取扱料2000円が算定できるので注意)
この書類がなければ、労災の治療費を請求ができないので、この書類を提出してもらうことが労災請求への第一歩になります。
もっと詳しい記事はこちらから
様式第6号
労災治療中、転院する場合に転院先の医療機関に提出する書類です。
この用紙を初回レセプトに添付する。
こちらも初診時にもらう書類ですが、取扱料は算定できません。
ちなみに、このときのレセの労災情報は”転医始診”となりますので注意が必要です。
様式第7号
仕事中に受傷し、非指定医療機関で受診する場合、いったん患者自身が治療費をたてかえた場合、この書類を提出することにより、治療費の償還が受けられるものとなっています。
用紙の裏がレセプト様式になっているやつです。
基本的には、労災の治療費以外にお金がかかった場合(例えば、交通費など)に補償を受けるときに必要な書類です。
また、労災指定病院で治療を受けていたが、患者自身が治療費をたてかえていた場合(健保を使って請求してしまっていた場合など)にも、この用紙を持参されることがあります。
作成料は請求できません。
詳しくはこちらも参考ください
様式第8号
労災治療中に休職した場合、給料の補償を受けることができますが、補償を受ける場合に必要な書類になります。
作成料はレセプトで休業証明書作成料(2000円)として請求できます。
レセプトに証明した期間を記載が必要です。
何か月か通っている患者さんについては、毎月持ってくる書類になります。
詳しい内容についてはこちらも参考ください
通勤災害の場合
通勤災害の場合も医療機関が証明したり、提出してもらう書類の種類は業務災害と同じになります。
名称と内容が若干違うだけなので、ここからは簡素化して説明していきます。
様式第16号の3
様式第5号の通勤災害版です。
詳しくは上記を参照ください。
様式第16号の4
様式第6号の通勤災害版です。
詳しくは上記を参照ください。
様式第16号の5
様式第7号の通勤災害版です。
詳しくは上記を参照ください。
様式第16号の6
様式第8号の通勤災害版です。
詳しくは上記を参照ください。
まとめ
通勤災害に関してはだいぶ簡単にしてしまいましたが・・・
要は、業務災害と通勤災害の書類名は若干ことなるが内容、証明するものとしては同じものです。
業務災害のほうが数が多いかと思われますので、そちらの書式名だけでも覚えておくと便利です。
そうすれば、通勤災害時でも、応用するだけなので、ぜひ、覚えておいてくださいね。
労災に必要な書類のまとめ