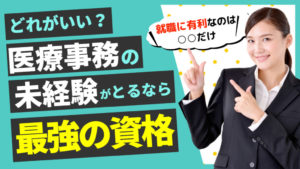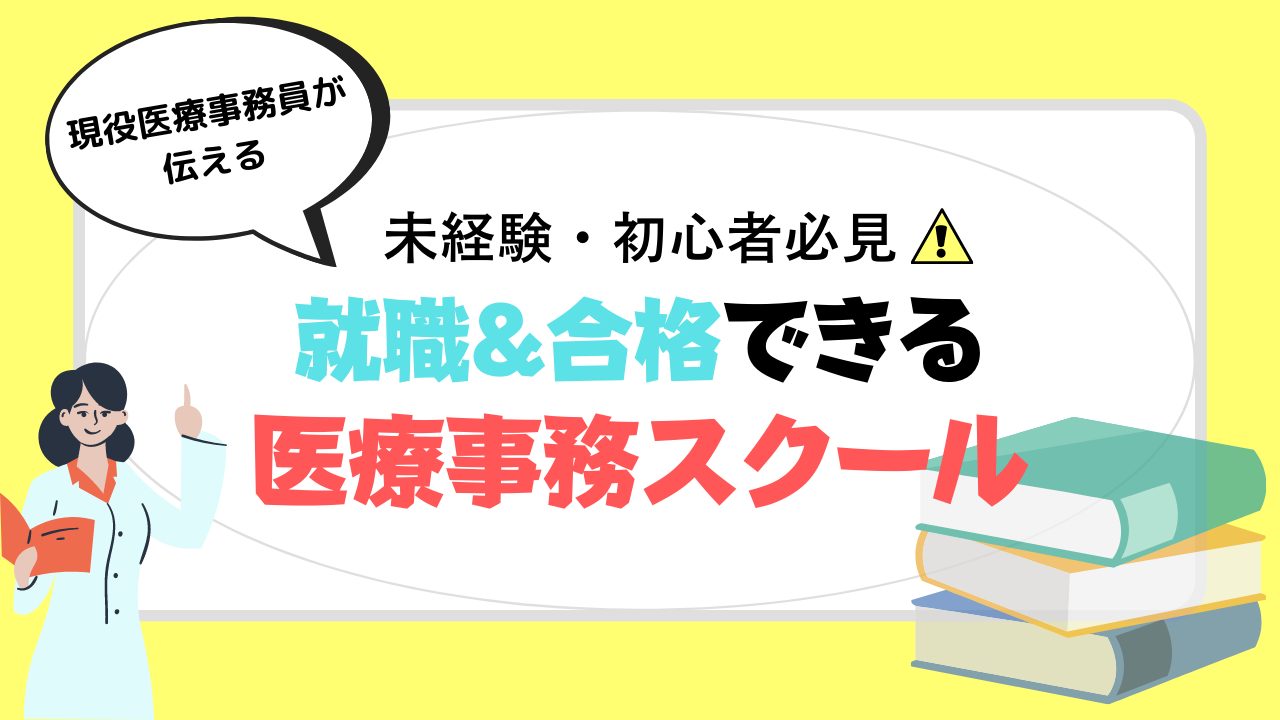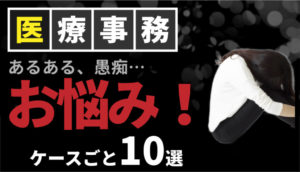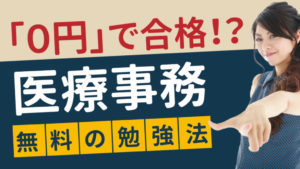通常、処方には上限の用量又は禁忌(同時に飲ませてはいけない処方)などがあります。
だいたいの場合は、レセプトのチェックソフトで注意・エラーがあがってくるので気づくことができます。(レセプトチェックソフトの初期設定ではだいたいエラー項目であがってくるはず)
ここで、上限の用量ですが、すべての患者が用法容量通りに処方しているというわけではありません。
もちろん、上限の用量を超えての処方は査定の対象となります。
しかし、みなさんお気づきだとは思いますが、上限用量を超えての処方って結構たくさんありますよね。
私も気になったので少し調べてみました。
薬局の先生に聞いてみた
私が実際に、薬局の先生に聞いてみた時の要点を書いていきます。
用法用量の1.2倍~2倍ぐらいまでは、大丈夫なのではないかというDrの判断で投与している。あくまでDr独自の判断です。いままで査定もされていないのでOKということでした。
用法用量に適宜増減ある場合に、数量がはっきり記載されている場合はその数量まで。逆にない場合は上記のように1.2倍から2倍ぐらいまで状況にあわせ投与している。
※適宜増減とは状況に応じて用量を変更しもよいということ
例えば
通常は用量が20~40mgまでだが、必要があれは1日80mgまで(容量の約2倍)は処方してよいことになる
他の例だと、適宜増減がはっきり明記されていない、この場合は極端な話でいえば用法用量の3倍の量とかでも適宜増減したとしてOKという考えになる。しかし、ここまでの量を適宜増減することはまずないので、あくまで例として受け止めてほしいです。
こんな感じで適宜増減している処方は結構あります。
しかし、レセ時期にあえて確認をするところはすくないかもしれません。常に薬局や院外薬局で確認をしてたりするからです。
とりあえず、気になったので調べてみました。
禁忌・併用注意の査定
禁忌処方がでていた場合は、ほぼ査定傾向にあります。
例として、処方でシロスタゾールを出している患者で病名に『うっ血性心不全』がついていたら、即効で査定されてしまいます。
ちなみに、併用注意や慎重投与であれば内容を確認し、処方しても大丈夫そうな場合は処方OKです。
最後に
禁忌や過剰投与された処方せんを持っていった、院外薬局もチェックしているので連絡がくることが多いです。
レセプトチェックソフトでエラーになったら確認するぐらいで、医事課での出番は少ないのかなと感じます。
それでも、なぜこういったことがおこるのか?といった疑問を持ち続けることが知識への向上へとつながっていくのかなとも思っています。