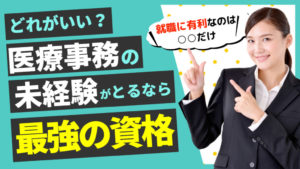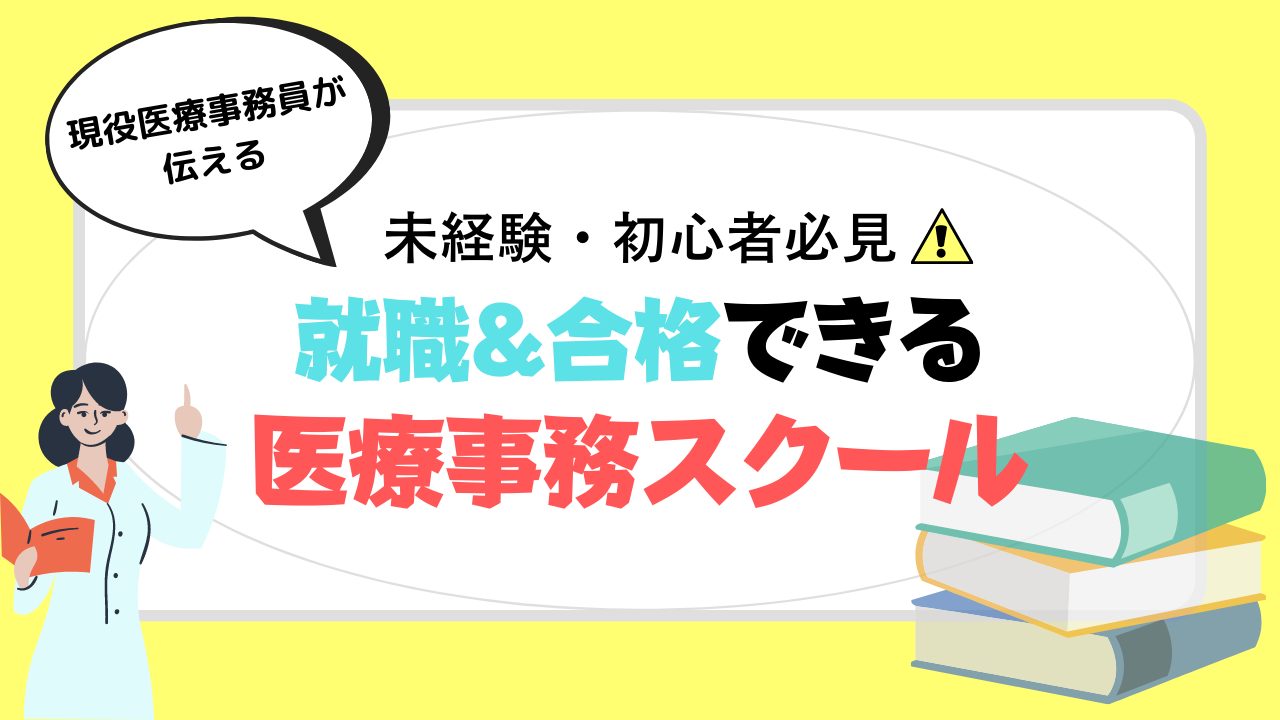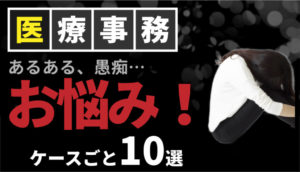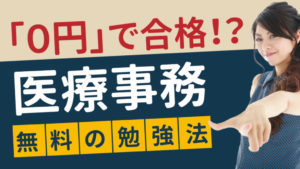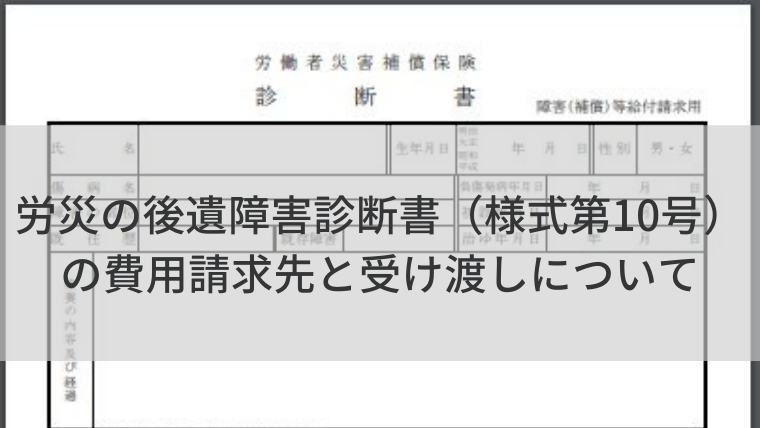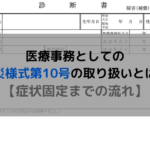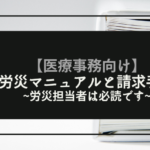そんな疑問にお答えする医療事務向けの記事です。
結論を先にお伝えすると
結論
- 費用の請求先は労災でレセプト請求
- 診断書は患者本人へ渡し、患者が労働基準監督署に提出する
ここらへんを詳しく書いていきます。
正式名称は「障害(補償)給付支給請求書(様式第10号又は第16号の7)」

ちなみに後遺障害診断書(様式第10号)が分からないという方はこんな書式のやつです。

参考リンク>>厚生労働省HP
※音声動画のほうがいい~という方はコチラも参考にされてください♪
後遺障害診断書の費用は労災レセプトで請求【令和2年3月31日から】
後遺障害診断書の費用は労災レセプトで請求です。
※ちなみに金額は4,000円です。
労働局労働基準部 労災補償課長 令和2年6月3日の事務連絡 より
労災診療費算定基準が令和2年6月1一に一部改定され、令和2年6月1日以降の被災労働者への診療に摘要されますので、その改定内容を~
~中略~
令和2年3月31日付けで省令が改正されたことに伴い、障害(補償)給付の支給を受けようとする被災労働者にかかる、「障害の部位及び状態に関する診断書(様式第10号、第16号の7」に要する費用(診断書料4,000円)につきましては、診療費請求書(含内訳)診機様式第1号(含2~5)にて請求できるようになりましたことを併せてお知らせします。
こんな感じで労働局から「後遺障害診断書はレセプト請求していいですよ~」って通知が来ています。
以前は患者本人から徴収していた
上記の改定があるまでは、医療機関によっては患者本人から費用を請求していました。
費用を支払い後、患者が自分で7号用紙を労働局へ提出し、払い戻しをうけるという流れでした。
7号用紙が分からないという方はこちらの記事もどうぞ
関連記事 労災、様式第7号の記入例と記載箇所
ここらへん、地域差あるみたいでした。
体験談
私の勤務していた医療機関では、様式第10号の費用は患者さんから徴収していました。
しかし、県外の事業所の対応をした際、様式第10号を患者へ請求しようとしたら、県外の労働局より「レセプトで請求しないのですか?」と突っ込まれました。
以前は、地域によって本人から徴収するケースとレセプト請求するケースがあったみたいですね。

後遺障害診断書は患者へお渡し後、患者が労働局へ提出する
- 患者が診断書を医療機関に持ってくる
- 主治医が診断書を作成
- 医療機関から患者本人へ診断書を交付
- 患者が診断書を労働局へ提出
といった流れになるかと思います。
患者さんの中には

みたいな事を聞いてくる人もいますが、そんなことはありません。
あくまで
- 手続き関係はすべて患者本人が行う
- 医療機関は治療と診断書の作成のみ
といった認識でOKかと。
注意すべき点は、後遺障害診断書を提出した時点で労災としての治療はできなくなるという点です。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
レセコンの設定は各医療機関で行う
レセコンの設定は医療機関によって異なると思うので、それぞれで設定していきます。
ちなみに、コメントコード対象ではないので、独自に作成しても大丈夫そうです。
※あくまで後遺障害診断書(様式10号)と分かるように。
紙レセプトの場合は、とりあえず診断書料の印字と金額が請求できさえすればいいので、適宜対応でよいかと思われます。
以上、参考になれば幸いです。