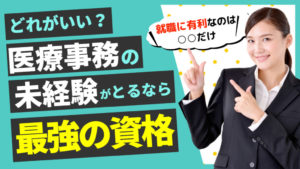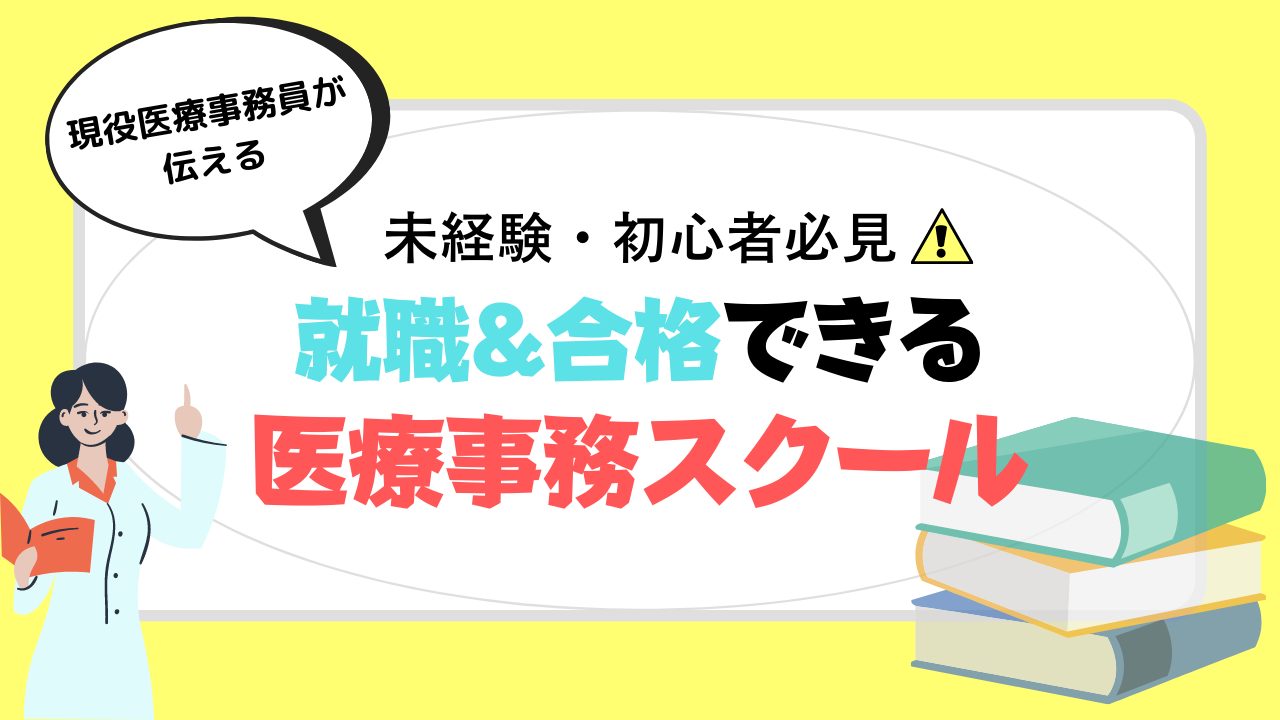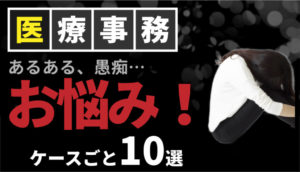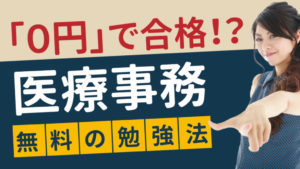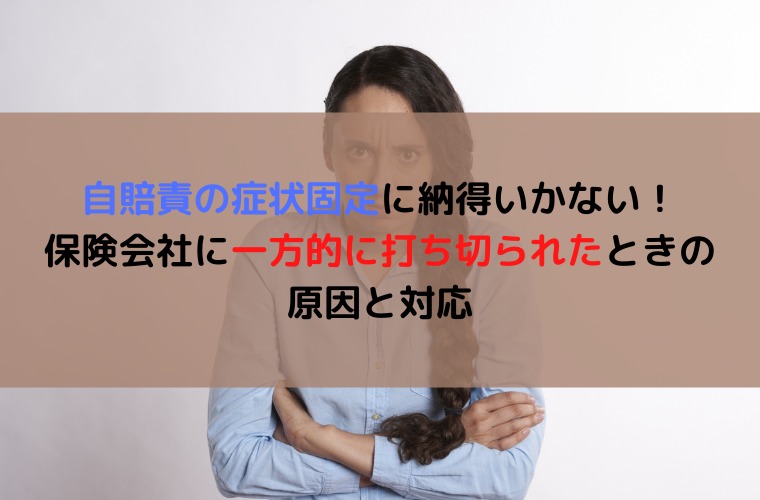私は現在、病院の受付業務で、事故患者の担当をしているのですが、その中で事故患者さんから多く言われるのが、『保険会社から勝手に治療費を打ち切られた』『症状固定に納得をしていない』といった内容の相談を受けることがあります。
交通事故の場合であっても、治療費の支払い関係については、あくまで患者と保険会社同士でのやりとりになり、病院は関与しないのが基本です。
ただ、医療機関も治療を行う中で、治療の継続や症状固定の判断を行っていきます。その継続か症状固定かの判断によって、患者さんの治療費が自賠責からでるのか、という部分が決まってきますので、まったくの無関係というわけにはいきません。
なので、今回は医療機関側から見た時の、『症状固定に納得できない』『訳も分からず打ち切られてしまった』という患者さんに向けて書いて行きたいと思います。
患者さんで、症状固定に納得していない場合や、勝手に打ち切りを言われて戸惑っている・・・
という方に、どうすれば治療を続けることができるのか?という事と、保険会社はどうして打ち切りを言ってきたのか?という事を、医療機関側からの視点でまとめてみました。
症状固定とされるとき
症状固定(しょうじょうこてい)とは、一般的に「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」の状態をいいます。
ネット上にもあるように、これ以上治療を行っても症状はよくなりませんよ。といった状態の時です。他のサイトの方が詳しく書かれているので割愛します。
この症状固定を判断するのは、あくまで病院の主治医になります。ここが今回の記事のキーポイントです。
このことは絶対であり、保険会社もこの判断に介入する事はできません。
むしろ、保険会社から、患者が納得いっていないのに勝手に症状固定と言われるというのは、保険会社の越権行為であり、許すまじき行為といえます。医者を馬鹿にしているのか?と思われてしょうがいないような行為です。
納得のいく症状固定までの流れ
本来の症状固定の流れで望ましいのは、
パターン①
- 状態が落ち着いた
- 医師より患者へ症状固定するか確認
- 患者が納得した上で症状固定
パターン②
- 保険会社から患者へ『そろそろ症状固定はどうか』と確認
- 患者から主治医へ『保険会社からこう言われた』と相談
- そのうえで主治医が判断
- 治療の必要が無ければ症状固定、治療の必要があれば継続する旨を保険会社へ連絡
といった上記のような流れが望ましいです。そうすることで、医療機関も患者本人も納得したうえで症状固定となるため、なにも問題はおきません。
問題となるのは、医療機関への相談なしに、保険会社が勝手に打ち切りを宣告することです。
保険会社も勝手に打ち切りにするわけではない
ここまで書くと、保険会社がすべて悪いように聞こえますが、そうではありません。保険会社も根拠があり、症状固定、打ち切りを患者さんへ通告してくるのです。
では、保険会社はどういった方法で、症状固定とする根拠を手に入れているのでしょうか?
それは、直接医療機関から情報を得ています。
事故をした初期の段階で、保険会社への提出書類の中に医療機関宛ての『同意書』があったと思います。
だいたいの内容としては・・・
『通院状況、治療内容、通院日数、患者の状態、レントゲン画像、検査の結果、主治医への問合せなどの個人情報を含む、交通事故に関する全ての情報の照会を保険会社が医療機関へ直接行い、それらを許可することに同意します』
といった内容のものです。
つまり、保険会社は患者の同意のもと、医療機関から患者の情報を聞き出し、治療内容や患者の状態から、「この患者は、症状も改善してきているから症状固定をしてもいいのでは?」とか「最近は通院をしていないので治療中止でいいのか」などといった感じで判断ができるわけです。
こういった医療機関から得ることのできる情報を元に、保険会社は患者に対し症状固定や打ち切りを勧告してくるわけです。
裏付けられた証拠がある
基本的には、診断書という形で毎月、医療機関から保険会社へ診断書を作成し送っています。
※これは、自賠責一括対応といって、治療費関係のすべての処理を保険会社へ一任するというシステムです。その中で診断書は必要不可欠なので、毎月出しているということです。
患者の治療状況は、主に診断書などから得ることができます。その中で、症状が改善している旨の情報があれば、保険会社はそこから患者へ症状固定を誘導していきます。
この診断書の他にも、症状固定では?と思われるような状態、長すぎる治療期間の患者に対しては、保険会社から病院へ直接問合せや診断書とは別で照会(治療状況の質問の書類)を行うこともあります。中には保険会社で、直接、病院まで来て主治医に話を聞きに来ることもあるぐらいです。
なので、こうった裏付けられた情報があるため、保険会社も堂々と打ち切り勧告をしてくるというわけですね。
同意書を提出しない
保険会社に有利になるような事だったら、最初から保険会社には”同意書”は提出しない!医療機関から保険会社へは情報を提供しないで欲しい!!となりそうですが、そうなった場合は、今度は患者側が行う手続きが面倒になります。
どういったことかというと、通常であれば、自賠一括対応ということで、手続きの全てを保険会社へ任せることができるので、患者は手続きをしなくていいので楽をすることができます。その分、上記で書いたようにすべての事故の情報は保険会社にはわたってしまいますが・・・
逆に、同意書を提出しない!となった場合は、今度は保険会社はそういった自賠責の手続き関係に干渉することができなくなります。
つまり、同意書を出さないとどういう事になるかというと、自賠責関係の手続きを全て患者自身で行わなければいけない。という面倒くさい事になります。だから、通常は同意書を書いて、最初から最後まで保険会社へお願いをしているということですね。
※基本手的には、自賠責の請求は”被害者請求”といって被害者が行わなければいけません。(加害者請求もありますが、今回はおいておいて)なので、自分で手続きや診断書関係を全て病院とかへ依頼をしなければいけないというわけです。
保険会社と医療機関とでは症状固定の認識が違う
保険会社と医療機関側では、症状固定に対して認識が少し異なってくる部分があります。(基本的な取り扱いは同じですが)
ざっくりいうと
保険会社 = 治療費の打ち切り(治療費メインに考えている)
医療機関 = 症状の改善、治癒(患者の状態をメインに考えている)
といった感じです。ホントは、症状の改善、治癒があっての症状固定なのですが、保険会社としては、はやく治療費の支払いを終わらせたいので、先に症状固定=治療費の打ち切りということで処理をしてしまおうとするのですね。
この保険会社の症状固定は、あくまで保険会社の(治療費の)事務処理上の中での症状固定というわけです。示談金や損害賠償を決定するための判断基準になります。
本来の医学的な症状固定は、主治医が決めるものですからね。
だから、保険会社のいうところの症状固定と、医療機関の症状固定とでは考え方が若干違うので、患者さんも「病院ではまだ治療できているのに」とか「主治医から症状固定とか言われてない」といった誤解がうまれてしまうことがあります。
医師が治療の必要性を認めれば継続できる
上記のように、医療機関と保険会社では症状固定の取り扱いの認識が違うので、症状が改善しておらず、主治医も治療の継続を認めているのであれば、症状固定ではありません。
保険会社の言う症状固定は、治療費の打ち切りのことを指しているわけですから、本当の治療に対しては主治医しか診断できません。なので、保険会社が終わりと言っても治療を続けることができるはずです。
しかし!!ここでは注意が必要です。
保険会社が打ち切りと言っているのに、患者本人と医療機関の判断で治療を行ってしまっては、トラブルになります。それは治療費の請求の関係です。
自賠一括対応をしていた場合、治療費はすべて保険会社が支払っていた(対応していた)と思います。それが、保険会社は治療費の支払いをしないと判断しているのに、患者が勝手に受診して治療費が発生しても、当然、保険会社は面倒を見ませんよということになってしまいます。
なので、打ち切り勧告された後の治療費は誰へ請求するのか?ということは注意しなければいけません。最悪、全額自費で患者本人が支払わなければいけない。ということにもなりかねません。(もし、そうなれば何十万という大金を支払わなければいけない可能性もあります)
でも患者本人が納得してればOK
上記でも、保険会社悪いように書いてしまいましたが、全てが悪いというわけではありません。
病院の主治医が症状固定と指示していなくても、患者本人の同意があり、保険会社の打ち切りに納得していれば問題ありません。
もし、症状固定として、残りの補償は示談金でまかなうとか、そういった方を重視しるのであれば、当然、そっちを選択すると思いますからね。
なので、
治療を続ける=治療中は示談金はもらえない
症状固定を認める=すぐに示談金をもらってしまう
といういう感じに判断していけるというわけです。
納得していないなら後遺障害認定診断書は提出しない方がいい
もし、保険会社から症状固定を促されても、自分自身としては納得していない場合は、受け入れないほうがいいのですが、その中で『後遺障害診断書』を書いてもらう。という選択肢を提示されることもあります。
納得していないなら、この後遺障害診断書は提出するべきではありません。
この後遺障害診断書を提出することで、医師も症状固定を認めていると判断されてしまうわけです。
もし、提出してしまえば、医療機関側も診断書によって、それらを認めていることになるので、症状固定として取り扱いをしていきます。
あとから、患者本人がやっぱり治療は続けたかったのにっ!!と言っても、保険会社と医療機関の両方で”治療の必要性はない”と認めてしまっているわけですので、自賠責として治療を続けて行くことはできなくなります。
※この後遺障害診断書については、名称は違いますが、取り扱い方としては労災の「10号様式」と同じ感じなりますので、そちらを詳しく書いた記事がこちらですので、参考までにこっちもご覧ください。
なので、納得しないうちはこの診断書は提出しないことをオススメします。
保険証を使うという選択肢は少し危険
症状固定をしてしまったけど、まだ治療を続けたいということであれば、当然、保険証を使って治療を続けることもできます。
通常の患者さんと同じ扱いになります。
しかし、治療をしたいからといって保険証を安易に使うのも注意が必要です。というのも、症状固定をした後の治療というのは、原因が事故によるものだったとしても、取り扱いとしては事故とは関係のない治療ということになります。(事故の治療は終わっているという考えのもとです)
患者本人は、事故としての治療と思ってやっていても、実際は、医療機関も保険会社も事故とは関係のない治療としてみています。
ここら辺は、事前の確認が必要ですね。治療後に、保険証を使用して治療を行ていた分が事故が原因で治療をしていたと証明するのは難しいはずです。もし、症状固定後に「とりあえず保険証を使っておいて後から保険会社へ請求しよう」などと安易な事を考えると、実際は支払ってもらえないということも十分に考えられますからね!
打ち切られたときのまとめ
本人が納得しないで保険会社に症状固定、打ち切りとされた場合の対処方法をまとめると
・後遺障害診断書は提出しない
・納得いかない場合は主治医へ相談
・保険会社も下調べした状態で話を進めている
これらの事を念頭においておけば、急に症状固定となることはないし、本人、医療機関も納得した上での症状固定になるとおもいます。
一番多いパターンは、保険会社から一方的に打ち切りを言われることです。恐らく、こういった一方的な対応が納得できない一番の原因なのかな、と思います。
保険会社の説明不足、高圧的な態度、などで腹が立つ!!ということもあると思いますが、患者さん自身もどういった理由でそうなったのか?という事を確認していく必要がありそうですね。
交通事故にあって心配な方へ
交通事故にあってしまい、ただでさえ心配なのに保険会社の担当と連絡がとれなかったり、対応が悪い、説明がない・・・
なんてことになったら心配は増えてしまいますよね。
しかも、体が痛い、事故後から体調が良くない、数日経ってからむち打ちの症状がでた・・・
となれば、気持ちと体のダブルの面で参ってしまいます。
そうなったときに、誰に相談したらいいかというと
- 警察もそこまで親身になって話を聞いてくれない。
- そもそも保険会社は対応が悪い
- 加害者へ直接は言いにくい
と、八方ふさがりの状況になっていることもあると思います。
そんな事故の手続き関係や体の症状の事で、どうしたらいいのか分からない!!という場合は、”交通事故サポート”へ相談してみてはどうでしょうか?
ここでは、交通事故で必要な手続きなどの疑問に思うことを無料で相談できます。
簡単な問合せ後、電話相談してみるというだけですので、『今後のことが不安』だったり、『現在の保険会社の対応に納得いっていない』、『体が不安でしょうがない』、『後遺症が残るのでは?』と感じている場合は、一度電話で相談してみてはどうでしょうか?
土日も相談を行っているので、日中忙しい方にもオススメです。
>>すぐに相談してみる