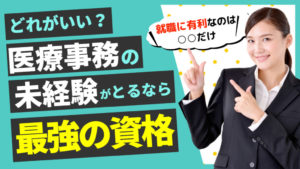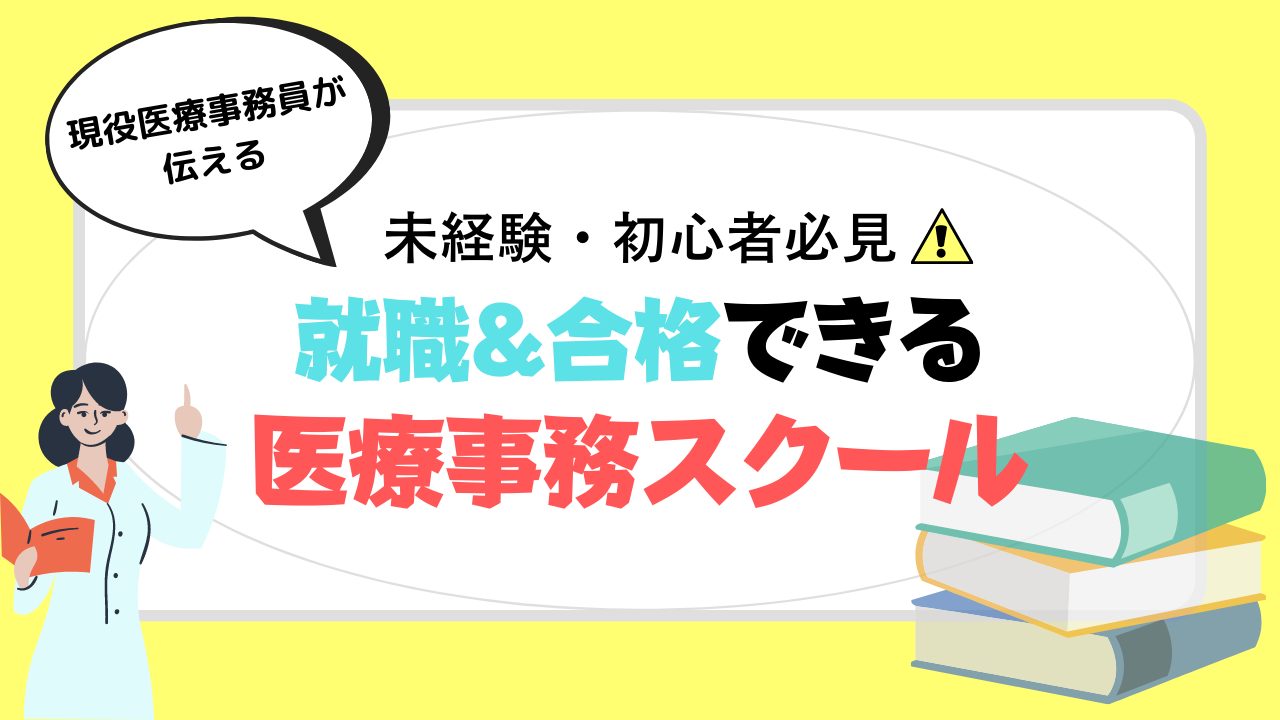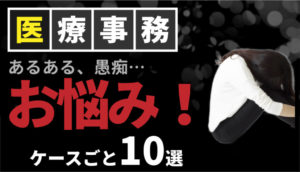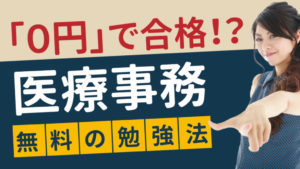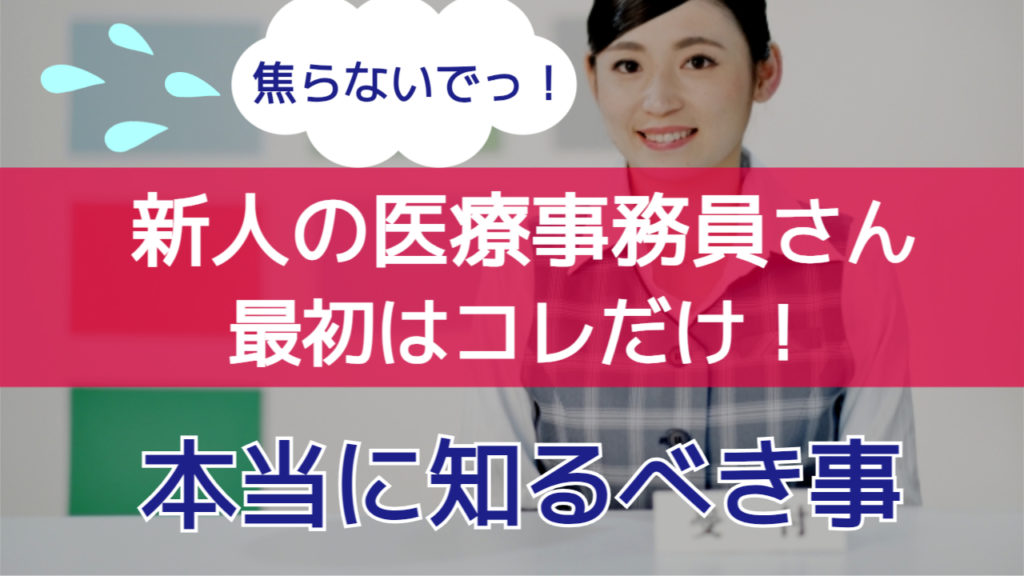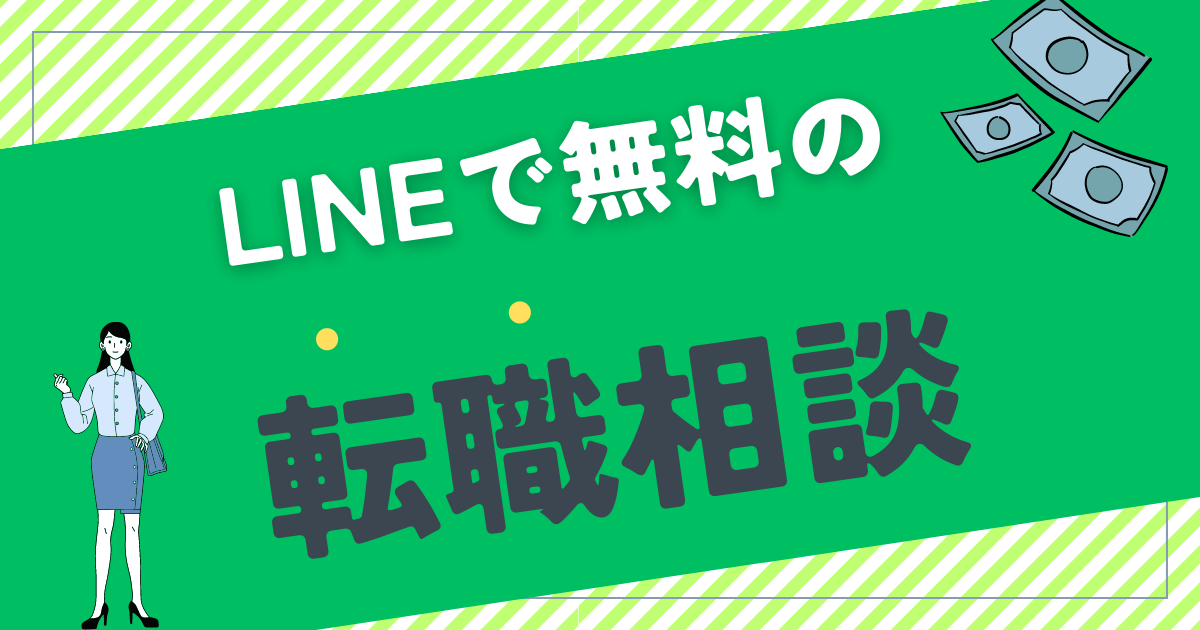こんにちは、医療事務員のアドバーグです。
今回の動画では、「医療事務の第一歩!新人さん必読!基礎を学ぶ3つのポイント」という内容でお伝えしていきます。
今現在
- これから医療事務を目指そうか迷っている
もしくは、
- 医療事務として働き始めたけど…
こんな方におすすめ
- 「まずは何をすれば周りに迷惑をかけずに仕事ができるだろか?」
- 「怒られないようにするためには何をすればいいの?」
- 「わからないことだらけで何からしたらいいのかわからない…」
と悩んでいる人の向けの内容となっています。

私自身、医療事務の現場で働き始めた最初の頃はミスばかりでほんとによく怒られていました。
そこらへんの私の実体験をふまえて、新人、未経験の医療事務員さんが最初にやるべき3つの大事なこと、という内容でお伝えしていきます。
このブログでは医療事務員がリアルな情報を発していますのでよろしくお願いします。
また、無料のライン相談もやっていますのでそちらもチェックしてみてください。
それではやっていきましょう。
▼動画でも解説しています。YouTubeはコチラから▼
医療事務の基本的な仕事内容
まずは医療事務の基本的な仕事内容をサラッと説明していきます。こういた基本的な業務があるからこそ医療事務に必要な知識ややるべきことがわかってきますからね。
まず、医療事務の主な業務は、受付や会計、診療報酬の請求や管理などがあります。医療事務は、患者さんや医師と密接に関わる重要な役割を担っています。そのため、医療事務として働くには、専門的な知識やスキルが必要です。
また、医療事務の仕事内容は、以下のように分類できます。
- 受付業務:患者さんの来院や予約を受け付けたり、カルテや診察券を管理したりすることです。患者さんに対して丁寧で親切な対応を心がけることが必要です。
- 会計業務:患者さんから診療費を領収したり、レシートや領収書を発行したりすることです。患者さんに対して正確で迅速な対応を心がけることが必要です。
- 診療報酬請求業務:医療保険などに対して、診療内容や費用を請求したり、管理したりすることです。診療報酬制度やコンピューター操作に関する知識やスキルが必要です。
- クラーク業務:病棟にあるナースステーションで働き、入退院に必要な書類のやり取りや費用の説明、施設の利用案内などを行うことです。特に入院費用については不安を感じる患者さんが多いので、わかりやすく説明することが大切です。
では、これらの業務にはどんな知識やスキルが必要なのでしょうか?
私が考える医療事務の基礎を学ぶために必要な3つのポイントをご紹介します。
医療事務の基礎を学ぶために必要な3つのポイント
ポイント1:医療用語の理解と正しい使い方
医療事務として働く上で、医療用語は欠かせません。医療用語とは、病気や症状、検査や治療など、医学に関する専門的な言葉のことです。
例えば、「胃潰瘍」や「高血圧」、「生化学的検査」や「内視鏡検査」、「抗生物質」や「点滴」などがあります。
これらの言葉は、カルテや診断書、レセプトなどに頻繁に登場します。
また、患者さんや医師とのコミュニケーションでも使われます。
そのため、医療用語の意味や読み方、書き方を正しく理解し、適切に使えるようになることが大切です。
では、どうやって医療用語を覚えるのでしょうか?私がおすすめする方法は、以下の3つです。
- 医療用語辞典やアプリを活用する
- 医師や先輩に聞いて覚える
- 実際に使ってみる
まず、医療用語辞典やネットを活用することです。
これらは、医療用語の意味や読み方、書き方を調べたり、することができます。インターネットで検索すれば、無料で使えるものもたくさんあります。

次に、医師や先輩に聞いて覚えることです。
医師や先輩は、医療用語に詳しい人たちです。というか専門の方です。
分からない言葉があったら、積極的に質問してみましょう。
その際は、ただ答えを聞くだけでなく、
- その言葉がどんな場面で使われるか、
- どんなニュアンスを持つか、なども確認しておくと良いです。
- また、質問した内容はメモしておいて、後で復習することも忘れずにしましょう。
注意ポイント
中には忙しすぎる職場で、みんな殺気立って質問しずらいということもあるかと思いますが、休憩時間やある程度暇なときであれば割と親切に教えてくれますよ。オドオドせず、勇気をもって質問してみるのも良い経験になりますよ。緊張感の中だからこそ覚えられることもありますからね。
あと、医療用語は実際に使ってみることが重要です。
医療用語は、覚えただけでは意味がありません。実際に仕事で使ってみることで、自分のものにすることができます。
例えば、カルテや診断書を書く時には、正確に医療用語を記入するように心がけましょう。また、患者さんや医師と話す時には、適切な医療用語を使ってみましょう。ただし、相手が理解できない場合は、わかりやすく説明することも必要です。もちろん忙しいので毎回毎回、正確に書いたり話す必要はなく慣れてきたら略語とかで全然OKです。
以上がポイント1:医療用語の理解と正しい使い方です。次にポイント2:医療機関の組織や業務の流れを把握するについてお話ししていきますね。
関連記事≫絶対にできる!未経験でも医療事務資格試験に独学で合格する勉強方法
ポイント2:医療機関の組織や業務の流れを把握する
について、もう少し詳しくお話しします。
医療事務として働くには、自分の仕事だけでなく、医療機関全体の仕事の流れや役割分担を理解することが重要です。
医療機関は、医師や看護師、薬剤師、検査技師など、様々な職種の人たちが協力して運営されています。
それぞれの職種には、専門的な知識やスキルが求められます。また、それぞれの職種が連携して、患者さんの診療や治療を行っています。
その中で、医療事務は、事務的な業務を担当しています。
では、具体的にどんな業務があるのでしょうか?医療事務の業務は、最初にお伝えしたように大きく分けて3つに分類できます。
- 受付業務
- 会計業務
- 診療報酬請求業務
受付業務とは、患者さんの来院や予約を受け付けたり、カルテや診察券を管理したりすることですよね。受付業務は、医療機関の顔とも言える重要な業務です。患者さんに対して丁寧で親切な対応を心がけることが必要です。
会計業務では、患者さんから診療費を領収したり、レシートや領収書を発行したりします。会計業務は、医療機関の収入に直結する重要な業務です。患者さんに対して正確で迅速な対応を心がけることが必要です。
診療報酬請求業務とは、医療保険などに対して、診療内容や費用を請求したり、管理したりすることです。診療報酬請求業務は、医療機関の経営に影響する重要な業務です。診療報酬制度やコンピューター操作に関する知識やスキルが必要です。

あと、余裕があれば他部署、例えば医師や看護師、相談員の業務の流れを軽く知っておくと、
「あ、今、こういう依頼を言ってきたのは、これから入院するかもしれないからかな?」
みたいな感じで状況がなんとなくわかってくるようになります。
関連記事≫医療事務(受付)なら忙しいのは当たり前?忙しすぎるあなたに伝えたいこと
以上がポイント2:医療機関の組織や業務の流れを把握するです。次にポイント3:患者さんや医師とのコミュニケーションスキルを身につけるについてお話しします。
ポイント3:患者さんや医師とのコミュニケーションスキルを身につける
医療事務として働くには、患者さんや医師と円滑にコミュニケーションを取ることが重要です。
患者さんや医師は、医療事務の最も身近な相手です。患者さんや医師とのコミュニケーションがスムーズに行われると、仕事の効率や品質が向上します。
また、患者さんや医師の満足度や信頼感も高まります。そのため、医療事務は、患者さんや医師とのコミュニケーションスキルを身につけることが大切です。
では、どんなコミュニケーションスキルが必要なのでしょうか?私が考えるコミュニケーションスキルは、以下の3つです。
- 聞くスキル
- 話すスキル
- 書くスキル
聞くスキルとは?
患者さんや医師の話を注意深く聞いたり、質問したりすることです。聞くスキルは、相手の意図や要望を正確に理解するために必要です。聞くスキルを身につけるためには、以下のことに気を付けましょう。
- 相手の目を見て聞く
- 相手の話を遮らない
- 相手の話に相槌やうなずきを入れる
- 相手の話を要約して確認する
- 分からないことは質問する
ポイント
特に高齢者は自分の言いたいことをうまく表現できなかったり、患者さん自身が理解できていなかったりなかなか要件がわからないことがありますので、上手に相手から話を聞きだす能力も大事になって来ます。
話すスキルとは?
患者さんや医師に対して明確で丁寧な話し方をすることです。話すスキルは、自分の意図や情報を正確に伝えるために必要です。話すスキルを身につけるためには、以下のことに気を付けましょう。
- 相手に合わせた言葉遣いやトーンを使う
- 簡潔でわかりやすい言葉を使う
- 話す前に頭の中で整理する
- 相手の反応を見て話す速度や内容を調整する
- 相手が理解したか確認する
医療事務が患者さんや職員に話すときも
「えーと、コレは、つまり、えーと」みたいに話すのはNGです。
相手に余裕があれ待ってもらえるかもしれませんが、多くの場合は忙しい、待たされてイライラしている場面が多いのでクレームの対象になってしまう可能性もあります。
書くスキルとは?
患者さんや医師に対して正確で分かりやすい書き方をすることです。
書くスキルは、カルテや診断書、レセプトなどの文書作成に必要です。書くスキルを身につけるためには、以下のことに気を付けましょう。
- 文法や表記法を守る
- 誤字や脱字がないかチェックする
- ポイントや順序を明確にする
- 不必要な言葉は省く
- 読み手が分かりやすいように工夫する
以上がポイント3:患者さんや医師とのコミュニケーションスキルを身につけるです。
関連記事≫「難しい…」新人の医療事務員が辞めたいと思うときの解決策を伝授
パート3、自信をつけたいなら勉強して資格は取りましょう
ここまで紹介した最初に取り組むべき3つのポイントで医療事務の新人さん、未経験者の方は十分に現場で活躍できるはずです。
自信をもって仕事に取り組んでいきましょう!!
ただ、中には


という方もいるかもしれませんね。
そんなタイプの方は、

医療事務の資格取得は、コミュニケーションスキルを高めるためにも有効です。医療事務の資格取得では、以下のようなことが学べます。
- 医療事務の基礎知識や法律・倫理・マナーなど
- 医療用語や診療報酬・保険制度など
- 医療機関の組織や業務の流れなど
- 患者さんや医師とのコミュニケーション方法やトラブル対処法など
医療事務の資格取得は、医療事務の仕事に必要な知識やスキルを体系的に学ぶことができます。
また、資格取得は、就職・転職・昇進などのキャリアアップにも役立ちます。資格取得は、自分自身への投資です。今日から始めましょう!
医療事務の資格のおすすめの勉強方法はコチラの記事を参考にしてください。
≫【医療事務スクール】医療事務のプロの圧倒的なおすすめ2選【コレで決まり】
-
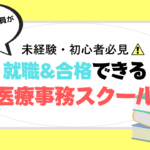
-
【医療事務スクール】医療事務のプロの圧倒的なおすすめ2選【コレで決まり】
続きを見る
以上が今回の記事内容になります。
この記事の内容が良かった、参考になったと思ったらグッドボタンもよろしくお願いします。
医療事務におススメの転職サイトは概要欄にリンクを貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。
私の転職の体験談も合わせて紹介しています。
またラインで無料の転職相談もやっていますので、そちらもチェックしてみください。
それではまた!
無料の転職相談はコチラ