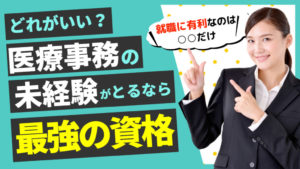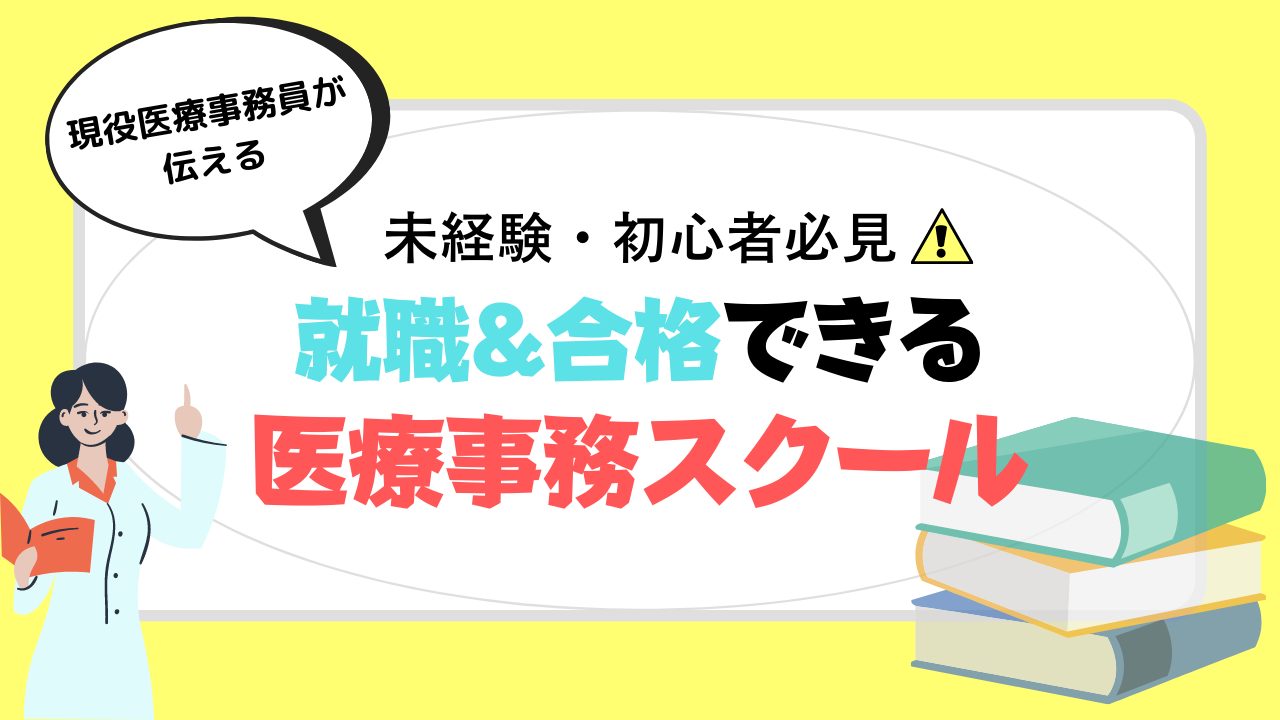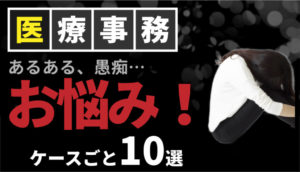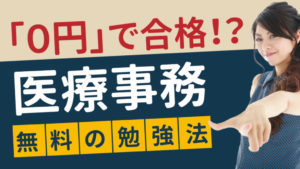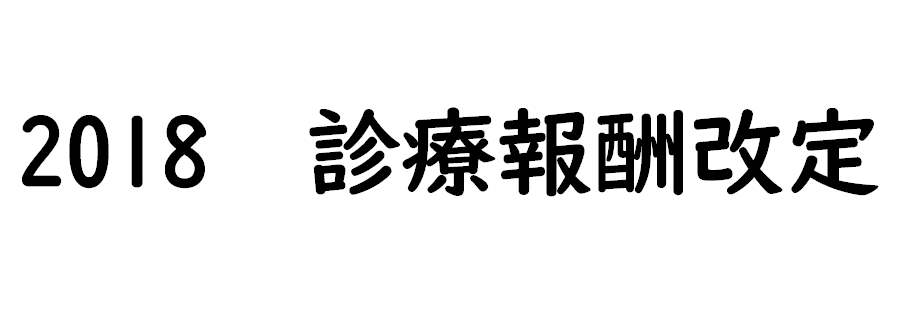今回の2018年改定から、ベンゾジアゼピン系薬剤(いわゆる精神系のお薬)は長期間投与する場合は、減算されることとなりました。
ベンゾジアゼピン系薬剤というとピンと来ないと思いますが、いわゆる精神系のお薬です。
不眠症や不安に対するものですね。
イメージ的には、精神科のある病院とかが使っているイメージをしている人も多いかと思いますが、実際は精神科がある病院だけが処方している訳ではありません。
精神科だけではなく、普通に内科でも処方しますし、精神科の無いクリニックでも処方する機会は多いでしょう。
精神薬といっても、全ての処方が専門医でないと処方しないというわけではありません。(もちろん、専門医でないと処方できない精神薬もありますが)
今回の改定の中で、ベンゾジアゼピン系薬剤の長期投与は減算の対象となるとされましたが、具体的にはどのようになって、どのような対策が必要なのでしょうか。内容をまとめてみました。
減算対象
不安の症状または、不眠の症状に対するベンゾジアゼピン系薬剤については、2018年4月以降の処方を対象として、1年以上連続して同一の成分を1日あたり同一量で処方した場合に処方料・処方せん料に減算規定が設けられました。
算定の点数としては、内服薬の7種類以上の場合と同じく処方料29点、処方せん料40点を算定することになります。
減算対象外になる場合
上記のように減算の規定が設けられたが、すべての対象処方が減算されるというわけではありません。
該当症状を有する患者に対する診療を行うにつき、適切な研修を受けた医師が行う処方、又は精神科医から直近1年以内に抗不安薬・睡眠薬について助言を受けている処方は除外されます。
適切な研修を受けた医師とは
適切な研修とは
「不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師」
「精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師」
となっています。
私の病院でも未確定な情報なのですが、今後、こういった精神薬を処方するうえで“適切な研修を受けた医師”に対する研修が多く行われることが予想されます。
恐らくは、オンライン研修などで簡単に受けられるような形式になるでしょう。
H30.9.14追記
普通に、医師会から研修の案内が来るようです。その研修の中で、
処方料・処方箋料に係わる『不安又は不眠に係わる適切な研修』を修了したものとして終了証を発行しているようです。
H31.2.19さらに追記
eラーニングみたいな感じで研修動画を見ることでも対応可能みたいです。
厚生労働省の疑義解釈の中にも記載があります。
参考リンク 厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その1)
医療機関としても、少しでも診療報酬の収益を高めていきたいので、研修程度で減算しなくて済むのであれば率先して研修を受けていくことが予想されます。
まとめ
減算の開始は2019年4月以降となりますので、それまでには研修を終わらせて減算を防いでいきたいところです。
また、精神薬とはいえ、一般の病院やクリニックにも十分に関連のある項目となっていますので各医療機関でも、今後の取り扱いには注意が必要ですね。
関連記事
※他の診療報酬まとめ
⇒【2018診療報酬改定】遠隔モニタリング加算の算定をわかりやすく説明しました
⇒【2018診療報酬改定】リハビリテーション総合計画評価料の算定をわかりやすく説明